海の贈りものを受けとる場所
「海辺で毎日をていねいに大切に暮らしたいな」と思い続けてきました。
海辺の暮らしの中で気づいたこと
海のすばらしさ・楽しさ
ウォータースポーツの楽しさ
などなどをご紹介できたらいいな。
気楽に生きたいと努力しています
海辺の田舎町で暮らしながら休日はウォータースポーツ三昧な生活をしていて、結構遊んでいるぼくがいうのもなんですが、自分自身では「マジメな社会人だよな」と思っています。
ちゃんと税金も収めていますし、約束は守りますし、待合せ時間も守ります。会社でも一応ちゃんと仕事してますし、クビにもならずになんとか勤めています。
ときどきぼくよりも気楽でノー天気な人に会うと「あぁ、こんな風に生きられたらいいな」と本気でうらやましくなります。あえて例を出すと芸能人でいえば高田純次さんなんて、いいなあと思います。あとはちょっと古いですが植木等さんとか…
芸能人の方は、仕事でキャラを作っていることもあると思うので、本当の本人は違うタイプかもしれませんけど、それはわからないのでどうしようもないですね。
やはり毎日楽しく生きるのが幸せでしょうし、気楽に無責任に生きられれば楽でしょう。なのでぼくは50代になってから、できる限り適当に気楽に楽しく仕事をするようにしています。自分ではすごく頑張って努力して、適当にお気楽に楽しく振る舞っているんです。これって簡単そうで結構難しいんですよ。
なので、たぶん周囲のぼくの印象は、海辺に住んで海遊びばかりしている気楽なオジサンということになっていると思うんですが、そういうキャラを作ってしまうと、仕事で小難しい案件とか来なくなるんですよねー。やっぱりイメージって大切なんだと思いましたね。こんなことなら若い頃からそういうキャラにしておけばよかったです。
さて、今日も休みなんですけど、朝からシーカヤックでもやろうかなと思っています。
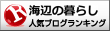
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
◆海辺の暮らしを紹介している雑誌をピックアップしてみました
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
PR
海辺の暮らしと都会での仕事のギャップが…
海辺の田舎町で30年近く暮らしています。休日にはウォータースポーツをしたり、海辺を散歩したりして、ノンビリ、のほほーんと暮らしています。
海辺の田舎町で暮らしていると書きましたが、実は平日は東京に通勤していまして、地元から東京に行くと、人の多さにウンザリします。
もう何十年もそんな暮らしをしているのに全然慣れなくて、人混みに揉まれると、イライラしたり、気持ちがグッタリ疲れたりします。
地元に戻ればそんな気持ちにはならなくて、ゆったりノンビリした気分になって、ほぼノーストレスなんですけどね。
人混みで疲れるというのは、ぼくだけなんでしょうか?
それともぼくが歳をとったからでしょうか?
妻にも聞いてみるんですが、やっぱり街に行くと疲れるといいます。
若い頃は東京に住んでいて、人の多い街で日々暮らしていたんですけどね。やっぱり若さですかね。
人混みが三度の飯より好きという人に会ったことがないので、もし会えたらその心持ちを伺ってみたいです。
ぼくの休日の海辺の暮らしは、ゆったりしていまして、朝はだいたい鳥のさえずりで5時とか6時に起きます(鳥の鳴き声が大きすぎて寝ていられない…)。
起きて最初にやるのは窓から海を眺めて、海況をチェックすることです。海況によって、スキューバダイビングをするか、シーカヤックをするか、サーフィンをするか、海辺を散歩するかを決めます。
海況チェックが終わったら朝ごはんを妻と食べます。朝ごはんを食べ終わったら、デッキでお茶をするんですが、ぼくはコーヒーを妻は紅茶を飲みます。お茶請けは妻が作ったクッキーとかパウンドケーキが多いですね。
デッキで海を眺めながらお茶をしている時間というのは、なかなか気持ちいいです。
お茶が終わったら、その日やると決めたウォータースポーツの準備をして出かけます。こういう日のスキューバダイビングは近場でセルフダイビングをするわけですが、遠出をするときは、事前に予約して、もっと早い時間に車で出かけます。
海で一日遊んで夕方帰宅します。帰宅したら、お風呂に入って、風呂上がりにデッキで海を眺めながらビールを飲みます。これがうまいんです。運動でほどよく疲れた身体にビールが染み渡っていく感じがします。
その後は晩酌をしながら夕ごはんを食べます。
季節と日によっては、その後、妻と夜の海辺を散歩することもあります。
そして10時頃に寝ます。
こうゆう週末の土日を過ごすと、平日の都会での仕事というのはギャップがあるわけでして、月曜日などはそのギャップに心身が慣れるのに時間がかかるほどです。しばらくは都会の生活のスピードについていけないんです。海辺で仕事ができればいいのになあ、などと贅沢な希望を持ってしまいます…
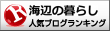
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
◆海辺の暮らしの良さを紹介している本をピックアップしてみました
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
潮風に吹かれているのが好き
潮風に吹かれているのが好きです。
というか空気が動いている空間にいるのが好きなんですが、それが潮風なら最高です。
細かい話しですが、家でも、冬の間は別として、窓という窓は開けっぱなしですし、車の窓も開けるのが好きです。
他にも似たケースでは、室内よりも室外の方が断然好きです。なので家では、室内のソファよりも、屋外のデッキの椅子に座っていることが多いんです。
空間が締め切ってある閉塞感が苦手なんだと思います。なぜなんだろうって考えるんですが、自分にはちょっとだけ閉所恐怖症の気があるかもしれません。日常生活ではほとんど不自由は感じませんけど…
そんなわけで風に吹かれているのが好きなんですが、潮風に吹かれているのは別格に好きです。潮の香り、ちょっと湿った空気の感じ…あれがいいんですよね。
あぁ、今すぐ海に行きたくなってきました。
海という自然に癒されて暮らしています
自然に癒されるというのはよく聞く話しですが、本当なのかなってときどき思います。っていっても、ぼく自身は海という自然に癒されているのは間違いないのですが…
あるタイプの人はどうして自然を求めるんだろうと考えたりします。というのも自然が好きじゃない人も結構いらっしゃるみたいなので…
ぼくは休日はたいてい海に出ていて、それが気分転換になっています。その時間がないと平日に都会で働くのに耐えられないくらいです。
癒されているかどうかはなんともいえないんですが、くつろげているし、気分も爽快になるし、気持ちも上がるし(古い言い方ですが、気分がルンルンになります)、仕事で起きた嫌なことも忘れられるし、海に行った日はよく眠れるし、などなど、精神面・肉体面でいろいろメリットがあるのは確かです。そういうことを考えると、これって海の癒しなんだろうなあと思います。
ぼくは間違いなく海という自然を求めています。自然がない環境ではたぶん生きていけません。その理由はどれだけ考えてもわからないんですが、幼い頃から自然の中で暮らし、遊んでいたからかもしれません。
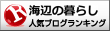
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
◆海という自然に癒されることを綴った本をピックアップしてみました
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
ウインドブレーカーの捨て時っていつなんでしょう?
ぼくは海遊びをするときに必要なのと、わりとアウトドアで遊ぶことが多いのと、傘を持ち歩くのが嫌いなので、ウインドブレーカーをよく使います。
ウインドブレーカーという呼び方が一般的なのかわかりませんが、よく山登りとかで使う、薄手の撥水力がある上着のことを指しています。ゴアテックスでできているウインドブレーカーが機能的にも値段的にも上等とされています。
ウインドブレーカーは海でもよく使うんですね。たとえばボートに乗っているとき、波しぶきで身体を濡らさないようにするために使ったりします。
で、最近悩みというほどではないんですけど、どうしたものかなと思案するのが、ウインドブレーカーがたまってしまうという問題なんですね。クローゼットを開けるとウインドブレーカーだらけ…
妻には何着か捨てるようにいわれるんですが、どれを捨てていいものやら判断がつきません。
どうしてこういうことになるかというと、ウインドブレーカーというのは買った直後が一番撥水力が高いんです。
そして使ったり、洗濯したりしていくうちに、だんだんと撥水力が落ちてくるんです。でも、どこも破れていないし、防寒着としても使えるので、服としては十分使えるんです。
それでたとえばぼくが今度、わりと長期のシーカヤックトリップを計画したとした場合、撥水力に不安がないように新しいウインドブレーカーを買うわけですね。水が浸みて身体が濡れると、気温が低い場合は低体温症になる危険もあるので撥水力には気を遣うんです。
ここまでで1着ウインドブレーカーが我が家に増えました。
で、古めの撥水力が落ちたウインドブレーカーを捨てればいいわけですが、撥水力が落ちたとはいえ、ちょっとした雨なら撥水するんです。一応ウインドブレーカーとしての役割を果たすし、衣類としてもどこも傷んでないし、捨てる理由がないんですよね。そういうウインドブレーカーが何着も溜まっていくんです。一番撥水力が低い物から捨てていけばいいのかもしれないですけれど、ぼくはそれができません。みなさんどうしてるのかな?
珊瑚礁の島って、やっぱりいいですよね!
ぼくは三浦半島の西岸の海辺に暮らしています。
会社は東京に通っていまして通勤時間が長くかかるんですが、海が好きで、海辺に移住しました。それくらいの重度の海偏愛者なんです。
休日には自分の家のそばの海で、スキューバダイビングやシーカヤックやサーフィンをしていまして、それはそれでとても満足しているんです。
でも、何年かに一度くらいは、無性に沖縄方面の珊瑚礁の離島に行きたくなります。やっぱり離島が好きなのと、空気がきれいなのと、陽射しが南国なのと、珊瑚礁の海のブルーが綺麗なのと、珊瑚礁のビーチが綺麗なのと、解放感があるのと…って、切りがないのでこれくらいでやめときますが、とにかく、沖縄の珊瑚礁の離島に行きたくなるんです。
自分の家のそばの海と何が違うんだろうと考えるんですが、やっぱり南国の珊瑚礁の島っていいんですよね。
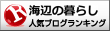
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
◆珊瑚礁の島旅ガイドの本をピックアップしてみました
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
サングラスはいろいろな種類を持とう
海遊びにサングラスは必需品です。
海でのサングラスには大きく3つの役割があると、ぼくは思っています
ひとつは目が日焼けして、白内障や緑内障などになるのを防ぐという健康上の役割があります。
もうひとつは、まぶしさを軽減する役割です。
最後は、水面のギラツキを少なくして、水中を見やすくするという役割です。
ひとつめについては、サングラスのレンズに紫外線を遮断する働きがありますので、サングラスをかけた時とかけない時では、目の痛さが違います。しょっちゅう海に出る人にとっては、この違いは大きいですね。
ふたつめは、夏の強い陽射しの日に実感します。特に海の上にいると四方八方、上からも下からも陽射しが来るので、まぶしくてしょーがないんです。それを和らげたいというわけですね。そういう場合は、色の濃いレンズのサングラスをチョイスするといいです。
最後については、偏光グラスというレンズを使っていると、水面のギラツキを抑えてくれて、見通しがよくなるのです。水の中もけっこう見ることができます。
以前の記事でもサングラスについてご紹介しましたが、今日はサングラスはいろいろな種類を持つといいよという話しです。
・海遊びをする人のためのサングラスガイド
・メガネをかけている人のためのサングラス
・紫外線から身を守れ!
サングラスのレンズは、紫外線透過率と明るさと偏光グラスかどうか、の主に3つの要素があるわけです。
海で使うサングラスは、紫外線透過率が低い方がいいですし、偏光グラスの方がいいんですが、
明るさをどうするかというのは、その時の海況によって違うと思うんです。
たとえば夏のすごく陽射しの強い日は、濃い色のサングラスで明るさを抑えた方がいいんですが、冬の曇った日に同じサングラスをかけると、暗くて見にくくなってしまいます。
逆もいえるわけで、色の薄いサングラスだと夏はまぶしいんですね。
というわけで、サングラスを選ぶ時は、色の濃さが違うものをいくつか買って、その日のコンディションによって使い分けるといいのではないかと思います。
ちなみに冬でも1日海の上にいるときはけっこう日焼けしますので、サングラスは必需品です。
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
ぼくの性格はいつからこんな風になったんだろう
ぼくはいつの頃からか、せっかちで、慎重で、かつ周囲に配慮して迷惑をかけないような性格になっていました。たぶん仕事でいろいろな経験をするうちに、そうなったんだと思います。
なにせぼくが仕事に就く前までの期間が22年間、ぼくが仕事をするようになって30年ですから、仕事をしている期間の方が長くて、ぼくの性格に及ぼす影響だって仕事によるものの方が大きいのもあり得ることかな?って思ったりします。
まあ、それはともかく仕事での振る舞いの反動で、休日は海辺でのんびり、ボーッと、マイペースに過ごすようになりました。海にいるときの自分が、おそらく本当の自分で、それ以外は社会でソツなく生きていくために矯正された自分なんだと思います。
ぼくの夢というか願望としては、マイペースで、周囲のことなんかお構いなしで、のんびりした性格になることです。これは本気でして、そうなったらさぞかし生きやすいだろうなと思うんです。
たまに周囲でそういう性格の人に出会ったりしますが、すごくうらやましいです。
でも性格というのはなかなかすぐに変わるものではないから、今の自分の性格で生きていくしかないですね。
◆仕事で疲れないコツを記した本をピックアップしてみました
シーカヤックの楽しさ
ぼくはサーフィンとシーカヤックとスキューバダイビングと船に乗るということをやっています。
今回は特にシーカヤックのことについて書きたいと思います。
ぼくがシーカヤックを始めたのが1999年のことでした。なので24年間やっていることになります。
シーカヤックを始めた理由のひとつ目は、もともと野田知佑さんの本が好きでしたから、自分もいずれはやってみたいと思っていました。
もうひとつ理由がありまして、それはサーフィンが関係しているんです。ぼくは1992年からサーフィンを始めたんですが、主に湘南の鵠沼とか辻堂あたりでサーフィンをしていました。そして日本の湘南のサーフィンの堅苦しさに、少し嫌気がさしていたんです。
サーフィンは波があるところでやるんですが、同じポイントでも、より波が高い場所にみんなが集まるんです。そして波に乗る順番というか、その波に誰が優先的に乗るかも決まっているんです。そのルールを守らないと喧嘩になることもあります。
湘南でサーフィンをした方なら分かると思いますが、波がブレイクするラインに、ずらっとぎっちりサーファーが並んで、さして大きくもない波を待って、いい波がきたら大勢のサーファーがそれを取り合うのです。なんとも窮屈な感じなんです。
そんな、せせこましいサーフィンをしているときに、ある日鵠沼でサーフィンをしていると、沖をシーカヤックでスイスイ漕いでいくシーカヤッカーを見ました。すごく自由そうな感じがして、いいなと思ったのが、ぼくがシーカヤック始めた理由のふたつ目です。
実際シーカヤックをしてみると、サーフィンとは違った面白さがあるのがわかりました。確かに自由なんです。サーフィンのように波に縛られる必要もないし、船舶免許が必要な動力を乗せた船のようなルールもないんです。大きな船のように着岸するための桟橋も必要ありません。SUPよりも荷物が積めて、ダブルブレードのパドルで漕ぐので効率がよくスピードもでて長距離も漕げますし、海上での安定性も高いのです。何よりも、シーカヤックには旅とか冒険とか自由という要素が含まれているんだと気がつきました。それがぼくを惹きつけました。
シーカヤックにキャンプ道具を積み込んで、人が来ることができない入江や無人島に上陸し、そこでまったく独りでキャンプするということができるんです。仮にそれを繰り返していけば、日本沿岸一周もできることになります。そんな自由さと可能性は、ぼくをワクワクさせました。
早速中古のシーカヤックを買って、シーカヤックの入門書を手本に、漕ぐ練習をしました。そしてだんだん遠くへ、多少荒れた海でも漕ぐことができるようになったんです。
そしてそれまで時々使っていたキャンプ道具や水や食料を1泊分積んで、シーカヤック1dayツーリングに出発しました。
目標としている浜は、人が陸路から立ち入ることができない、小さな入江です。入江に着いたら、テントを張って、荷物をテント入れました。そしてコーヒーを飲んでひと休みです。やってみて気がついたんですが、他人が来ないことがわかっていると、心理的にとても安心でき、開放的になります。ぼくの場合は寂しくはなりません。一人行動が好きなんです。というか一人で周囲に気兼ねすることなく居られる心理的な自由感は、これまでに味わったことのないものでした。これを契機にぼくは単独シーカヤックお泊まりツーリングに行くようになりました。
風が通る道
海でウォータースポーツをすると自然の様子に敏感になります。それはウォータースポーツをより楽しむことや、自分の身を守ることに直結しますから、当たり前といえば当たり前かもしれません。
たとえば風なんですが、海をシーカヤックでパドリングしていると、風が通る道があるのがわかります。
たいていは陸側に山がいくつか連なっていて、その間に谷があって、谷の部分から風が吹き出てくるというパターンが多いですね。
それから岬を越えるあたりにも風の道があったりします。
風の道は、風が吹いているところの水面にさざ波が立ったりしますからそれでもわかります。もちろんさざ波が分かるくらい海が凪いでいる日に限りますが…
風の道は、パドリングしているとその道の部分だけ、風が強くなります。一瞬あせるんですが、周囲を見回すとその部分だけが波だっているので、その部分を漕ぎ渡ってしまえばなんてことありません。
セイリングやウインドサーフィンをする人は、風の吹いているところ、ブローが吹いているところを見つけるのがもっと上手です。
こんな感じでウォータースポーツをしていると、自然の様子に敏感になるんですが、その敏感さは陸にいるときにも発揮されます。なので陸でも風の道を見つけたりします。やはり谷間や川に沿って風が吹くことが多いようです。よくわからないのは高層ビルの近くでして、高層ビルの真下は間違いなく風が強いんですが、高層ビルが林立している街などは、高層ビルとビルの間で渦巻くような風が吹いていたりします。
自然の様子に敏感になると、普通なら見逃してしまうようなことを感じ取れて、ある面では豊かな日々が送れるといえるかもしれません。
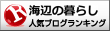
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
◆風の読み方をガイドした本をピックアップしてみました
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
カテゴリー
最新記事
(09/20)
(09/14)
(09/13)
(08/31)
(08/30)
(08/24)
(08/23)
(08/17)
(08/16)
(08/10)
(08/09)
(08/03)
(08/02)
(07/27)
(07/20)
(07/19)
(07/13)
(07/12)
(07/06)
(07/05)
(06/29)
(06/28)
(06/22)
(06/21)
(06/15)
最古記事
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
アーカイブ
ブログ内検索
PR
カレンダー
最新コメント
[10/31 TOM]
[06/10 TOM]
[06/10 TOM]
[11/09 porn]
[07/09 和]
PR
google


