海の贈りものを受けとる場所
「海辺で毎日をていねいに大切に暮らしたいな」と思い続けてきました。
海辺の暮らしの中で気づいたこと
海のすばらしさ・楽しさ
ウォータースポーツの楽しさ
などなどをご紹介できたらいいな。
走錨注意報について
海上保安庁の無線を聞いていると、ときどきというかよく走錨注意報という言葉がでます。これは、風が強いので、錨を降ろして停泊している船が動いちゃうかもしれないから気をつけろ、という注意です。
で、ぼくは錨を降ろすような船は持ってませんが、シーカヤックをやるので、この注意報を海の荒れ具合の目安にしています。
風向きや地形によりますから、この注意報が出ているからといって、海に出られないほど荒れているとは限りませんが、そんなに穏やかな海でないことは確かです。
相応の器材や心構えで海に出ます。
以前の記事でも書きましたが、この注意報はメールでも受け取れるので、もし関心がある方は登録してみてください。
→海上保安庁 緊急情報配信サービス
◆シーカヤックの関連本をピックアップしてみました
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
PR
自然の中へ入っていくときは、天候の急変には要注意ですね
ぼくの家は海のそばにあります。窓からは海が見える、そんな距離感です。なので休日はわりと海に出たり、海辺を散歩したりするんです。
穏やかな日の海は、湖のようにベタ凪です。
それなのに台風などの強風が吹くと、別物のように荒れます。その時の波の大きさや力強さはすごいものです。何度見てもビビってしまいます。
同じ海なのに、天候が悪化するとここまで変わるんだと驚かされます。自然のパワーに対しては、人間の最新技術をもってしても防ぎきれないよなーと、毎年のように各地で起きる自然災害についても納得してしまいます。
たまにベテランのセイラーやダイバーや登山家などが遭難することがありますが、自然の天候の急変は、事前に天気情報を収集していても、100%予想どおりになるとは限らないので、一旦荒れてしまうと、命が危険にさらされるんだろうと思います。
ぼくの経験でも危ない目に遭ったことは数知れずありますが、そのひとつとしてこんなことがありました。
午前中に海に入るときは穏やかで、天気予報も今日は風も吹かず穏やかという状態だったんです。そんな状況でシーカヤックで、自分の家のそばのビーチからエントリーしたんです。
漕ぎ始めた頃はベタ凪に近い状態だったので、調子よく漕いでいました。途中で昼メシを食べようと、人が来ない入江に上陸。アルファ米の五目ご飯を食べて、食後のコーヒーを飲んでゆっくり休憩しているうちに、少し風が出てきたなと感じました。すると風速が当初5m/sくらいかなと思っていたところ、あっという間に8〜10m/sくらいに上がってきました。そして当然ですが風速が増すに連れて海面は波立ってきました。
ぼくはヤバイなと感じ、すぐに引き返すことにしました。しかし波がだんだん高くなってきて、大荒れまではいきませんが、かなり荒れている状態に。沈はしなかったんですが、大きめの横波を一発食らったらヤバイ状況でした。結局エントリーした自分の家のそばのビーチに帰るのは諦めて、途中のビーチになんとか上陸しました。
そこからシーカヤックの海着のままバスが走っている国道まで歩き、バスに乗り、自宅のそばのバス停まで戻りました。自宅に帰るとすぐに車を出し、上陸したビーチまでシーカヤックをピックアップしに行きました。ぼくの車にはいつもキャリアを付けているので、こういうときは便利だなと思いました。
話しが長くなりましたが、ベタ凪の海が数時間でかなり荒れた海になるわけで、海は油断禁物ですね。
自然の力に対しては、人は常に謙虚で、保守的で、警戒心を持つべきなんだろうと、自分を戒めています。
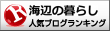
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
◆マリンスポーツをする人のための気象の本をピックアップしてみました
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
海辺の土地の見極め方・分類方法について~海辺に住みたいと考えている方へ~
この文章を読んでいる方の中には、「これから海辺に引っ越したいな!」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
でも、一口に海辺といってもいろんな土地があります。「どこを選んだらいいの?」と思っている方に参考になればと思い、この記事を書きました。
以前にも海辺に住みたい人にとってどのような立地を選ぶかについていくつか記事を書いていますので、もしよければご覧ください。
その際参考にさせていただいていたのが『いつかは海辺の家で暮らす』という本です。著者である加藤さん・植村さんは、海辺の家のロケーションをA-1・A-2・B-1・B-2の4パターンに分けています。
Aは海岸線に建つ場合で、Bは海岸線ではないが海まで徒歩圏内と大きく分かれます。
A-1は平地にあって目の前が海の家
A-2は崖っぷちなどの高台にある家
B-1海辺から内陸に少し入った家
B-2海辺から内陸に少し入った高台の家
これは画期的で合理的な分類ですね。自分が住みたい土地のイメージを明確にするのと、実際物件を探す際に、不動産屋さんに伝えやすいというメリットがあります。
で、ぼくは自分の好みの立地を考えていくうちに、もう少し他の要素があるんじゃないかと思いました。
加藤さん、植村さんのアイデアをパクったとか剽窃したとか、そういうことではありません。
アイデアを発展させた!という感じで受けとっていただきたいと、かように考えるわけであります。
あるいはお二人にインスパイアされた!と意味なくカタカナなど使ってオシャレなイメージにしちゃいましょう。
a:海岸からの距離
b:高さ(標高)
c:陸の地形(平野か山が迫っているか)
d:海の地形(砂浜か磯かなど)
e:土地の用途(宅地か山林か農地かなど)
f:町からの距離(市街地か田舎か)
g:その他
これらの要素があるとぼくの住みたい立地がある程度表現できるのです。
そしてaからfそれぞれにさらに要素があります。
それを1から順に番号を振ってみます。
ちなみにぼくの好みの立地を表現してみると…
a1:b2:c2:d2:e2:f2
ということになります。
ぼくは海に近くて、標高が20m~30mくらいの斜面か丘で、山地かリアス式の土地で(平野はあまり好きではありません)、小さな砂浜と磯があって(そういう砂浜はたいてい両端に磯や岬があるので)で、山も近くて、あまり建て込んでいない田舎が好きです。
その他の好みとして、海から家までの間に道路が通っていないところが好きです。湘南の134号線のような大きな道が通っているような土地は好きではありません。海と隔てられている感じがしますし、海に行くのにいちいち信号とか横断歩道とか面倒くさいじゃん。
また、家から海まで階段がない場所が好きです。スロープになっていると、海遊び道具をカートに載せて運べるからです。
それから(まだあるんですよ)家が道路のどん詰まりになっているところが好きです。なぜならその道を通る人が必ず自分の家に用があるからで、通過するためだけの人が通りません。そういう土地ってすごく安心感があるし、プライバシーが保てるんですよね。
さて、それでは各要素の長所・短所について、ぼくの考えをまとめます。
a:海岸からの距離
この項目は海好きな人でも、ウォータースポーツをやる人か、海を眺めるのが好きな人かによって好みが出ます。
ウォータースポーツが好きな人なら、海に近い方がいいでしょう。ちなみにぼくの経験では、徒歩5分以内でないと、サーフボードやシーカヤックなどを運ぶのが億劫になります。
ただし、海から近いと塩害、砂の害、津波など心配なことも増えます。ぼくの知り合いで海岸べりの防波堤のギリギリのところに家を建てた人がいますが、ちょっと海が荒れると家全体が潮をかぶってしまうそうです。この人なんかは海辺に住んでいるというより、もはや海に住んでいるといっても過言ではない、苦しゅうない、近こうよれ、よっしゃよっしゃ、あっぱれあっぱれ…
一方、海からあまり離れてしまうと、それってもう海辺じゃないじゃんということになり、何のために海辺に移住したのかわからなくなります。なので離れるといっても徒歩で20分以内じゃないの?というのが、ぼく的な目安です。
b:高さ(標高)
これはイメージしやすい項目ではないでしょうか?
海辺の高台に住むと眺めがいいもんねー、てなことです。
ただ注意が必要なのは、ウォータースポーツをする人で大きな道具を運ばなければならないような場合、たとえばシーカヤックとかウインドサーフィンとかセイリングとかですけど、そういう場合はあまり急で標高の高いところに住むと、海に行くのが億劫になります。いえいえ、海に行く時は下りだからまだいいんですが、海で遊んで家に戻るときに坂道を登らななくてはならず、立地によってはたいへんなことになります。
熱海はずーっと上の方まで別荘地が続いていますが、あまり上の方は海辺という感じがしませんもんね。
ぼくが海辺で土地を探すとしたら、aとbのバランスに一番こだわると思います。
ぼく的にはウォータースポーツをしますので、海辺に近い方がいいなあと…
一方、家にいるときも海を眺めたいので、ある程度高台に住みたいのです。なので、ウォータースポーツの器材を運ぶのに苦にならない程度の高台(標高20mとか30mで緩やかな坂道って好みがいちいちうるさいでしょう)で、海まで徒歩3分以内という立地が理想です。

c:陸の地形(平野か山が迫っているか)
地形ってけっこう大事です。タモリさんほどじゃないですが、ぼくも結構地形好きです。
茅ヶ崎とか九十九里みたいな土地って、海からほとんど標高が上がらず、平野がズーッと内陸まで続いています。そういう土地が好きな人もいます。
平野のいい点は、家が建てやすく、移動が自転車とか徒歩でラクラク・ランランというところ。悪い点は津波が来たとき、逃げる場所がないということです。あと、たいていそういうところって家が建てやすいので、建て込んでいるんですよねー。それに竜巻が起きやすい場所ってたいてい平野です。
ぼくは海が好きですが、山や森も好きで、見た目に変化のある地形が好きです。そういう点で平野は好きではありません。
一方、熱海とか熱川とかって山が海に迫っている地形で、平野がほとんどありません。ぼくはこういう土地の方が好きです。
山が迫っている土地のいい点は、眺めの良さが期待できるということ、森になっていることも多いので緑が豊かで鳥なども多く、田舎暮らしをしている感が満載です。悪い点は坂道が多いので移動がたいへん、平地が少なく住む場所が少ない、崖崩れがあるかもしれない、地形によっては風や雨が多いかもしれないということです。
そしてリアス式の海岸というのは、志摩とか有名ですね。油壺なんかはリアス式海岸ではないかもしれませんけど、そういう雰囲気を醸し出していますが、入り江がたくさんあって、丘から海までドロップオフ的にストンと下がっている立地です。陸地は山というより丘というのが相応しい高さだといえます。
リアス式の海岸のいい点は入江がたくさんあり、水深も深くなっているので、天然の良港になりうること、変化に富んだ地形が楽しめることです。悪い点は平地が少なく住む場所が少ないこと、坂が急なことでしょう。
また、島もこの項目に含めてもいいでしょう。ぼくも島好きですが、島は島ならではのよさがあります。一方陸続きではないので、交通の不便さはあります。
d:海の地形(港か砂浜か磯かなど)
サーフィンをする人は海が砂浜になっている方がいいですよね。一方スキューバーダイビングやスノーケリングをする人は、磯や珊瑚礁になっている方がいいでしょう。また釣りやボートやセイリングをする人は港があった方がいいかもしれません。また複数の要素が近接している立地もあるかもしれません。
珊瑚礁なんて憧れますが、沖縄とか小笠原とか海外が選択肢に入ってきて、ぼくはちょっとそこまでは…という感じです。
ちなみにぼくはそんなに長くない砂浜が好きです。そういう砂浜はたいてい両端が磯か岬になっているので、砂浜と磯両方を備えていて、ぼくのようにサーフィンもするダイビングもするという人にはピッタリの地形です。
e:土地の用途(宅地か山林か農地かなど)
いわゆる不動産関係の人が地目と呼ぶ項目です。不動産を買う場合、気になる項目ですが、ここではその土地周辺の雰囲気も指します。地目が宅地ならばだいたい一帯が住宅地で、家が建て込んでいたりします。上下水・電気などのライフラインはキチンと整備されていたりします。暮らしやすいですよね。
山林や農地だと、周囲に家のない土地かもしれません。また、場所によっては水道と電気を引かないといけないかもしれません。
家を建てるときも宅地なら問題なさそうですが、別に山林でもその分安くていいという方はそれでもいいでしょう。一方、農地だと家を建てる際に制限がありますから、そこは要チェックでしょう。
f:町からの距離(市街地か田舎か)
田舎暮らしをしたい方は、あまり建て込んだ市街地を好まないかもしれません。一方、生活の利便性を考えると、スーパーや病院などが近い方が便利です。自分の好みをはっきりさせるか、あるいはバランスをとるか、自分の考えを整理した方がいいのではないでしょうか?
ぼくは今近くのコンビニまで車で10分、スーパーまで15分程度のところに住んでいますが、別に不便ということはありません。好みとしてはもう少し不便なところでもいいかなーと思っています。スーパーまで車で20~30分くらいならぜんぜん許容できます。
今は、宅急便や郵便の配達がしてもらえるところなら、かなりの生活必需品がネットで注文できるので、その辺は思い切って田舎に住むという選択もありですね。

g:その他
これについては、先ほど書きましたが、海から家までの間に道路が通っていないところ、とか、家から海まで階段がなくてスロープになっている、とか、家が道路(できれば私道)のどん詰まりになっているところ、といった好みがあります。
おそらくこれは人それぞれいろいろあるんだと思います。
四角い土地がいいとか、南向きじゃなきゃだめとか…
さてさていろいろ長く書いてしまいました。
これらの分類は、細かくて面倒くさそうですが、自分の理想の海辺の立地を明確にできるというメリットがあります。
もしあなたが海辺への移住を考えていらっしゃるなら、そして自分の理想の立地がイマイチはっきりしていないなら、上の分類を参考にご自身の希望を明確にしてはどうでしょうか?
海にいる人はみんな楽しそう!
ぼくは海が好きなんですが、海が好きな理由は108つはあるんですが(たぶん)、そのひとつに「海にいる人は、みんな楽しそう」というのがあります。
それはやっぱり海が好きな人が海に来ているから、当然そうなるんでしょうけど、それ以外にも海の力というのもあるんじゃないかと思うんです。
海の広さ・青さ、空の広さ、太陽の光、潮風、波の音、砂浜の感触、人口密度が低いこと、非日常の感覚…そんないろいろな条件が重なって、みんな楽しそうなんじゃないかなあって想像します。
で、楽しそうな人が多い場って、やっぱりみんな楽しそうになって、それを見ているぼくも楽しくなるわけです。
波打ち際を子供が駆け回って、犬を散歩させている人がいて、ビーチチェアに寝そべって焼きに入っている人がいて、サーフィンする人、SUPをする人、シーカヤックをする人、シュノーケリングをする人など、みんな楽しそうです。こんな平和な日々がずっと続くといいなあと思ったりします。
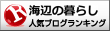
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
◆海で健康になるヒントが書かれた本をピックアップしてみました
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
ぼくのダイビング器材のその後
以前ぼくが使っているダイビング器材を紹介しました。
器材で何を買おうか迷っている方の参考になればいいなと思ったのです。
その後、使っている器材がだいぶ変わったので、改めてご紹介したいと思います。
その後はこんな感じになっています。
・マスク GULL マンティスシリコン
→いまだに同じ物を使っていますが、近眼が進んだ(本当は老眼も進んでいるので、老眼対応のレンズにしたいです)のでレンズの度を変えました。当初透明だったシリコンがだんだん黄ばんできて、ちょっとみっともないですが、構わず使ってます。
・スノーケル TUSAの古いやつ
→GULL S-3172 カナールステイブル ブラックシリコン セイフオレンジに替えました。やっぱり20年以上使っていると、さすがにシリコン部分が劣化しますね。それからスノーケル内部にカビが発生していて、キッチンハイターしたんですが、キレイにならなかったので買い替えました。オレンジにしたのは、安全面で少しでも目立つ方がいいかなと思ったからです。
・フィン CRESSI Master Frog or GULL MEW
→SUPER MEW XXに替えました。やっぱブーツを履いてないと岩場を歩くとき不便なので…SUPER MEWにはしませんでした。前に使っていたCRESSI Master Frogはよかったんですが、プラフィンで、ヘタってきたので買い替えました。CRESSI Master Frogはボートダイブでは大きすぎて他のダイバーに邪魔になっていたのが玉に瑕でした。
・ウェットスーツ BREAKER OUT モデル名や型番は忘れました。
→いまだに同じ物を使っています。でも、さすがに10年くらい着ているので、膝あたりの生地がボロボロです。来年あたりに買い替えかな…
→いまだに同じ物を使っています。でも、さすがに10年くらい着ているので、膝あたりの生地がボロボロです。来年あたりに買い替えかな…
・BCD SCUBAPRO CLASSIC 何世代のか忘れました or Zeagle レンジャー
→いまだにSCUBAPRO CLASSICをメインで使っています。水中での姿勢を自在にコントロールできるので、SCUBAPRO CLASSICは使いやすいです(Zeagleなどの背面フロートのBCDはどうしても下を向きがち)。t
・レギュレーター SHERWOOD ブルート
→Bism Ti ネレウス RX3400DL。ダイビング中にセカンドステージが引っ張られるような感じが気になっていたので思い切ってスイングヘッドのBismにしました。あとやっぱり軽いレギが欲しかったのでチタンにしました。これは大満足です。SHERWOOD ブルートは10年以上使ったので、まあ元は取ったかな…
・オクトパス Air2
→変わらず。やっぱりオクトがブラブラしていると水中で邪魔です。
・ダイブコンピューター アラジン スマートプロ
→15年使っていて壊れたので、ガーミン MK2iに替えました。古いダイコンから一気に最先端のスマートウォッチタイプのダイコンになったので、隔世の間があります。いやー便利。ガーミン MK2iは、スキューバダイビングだけでなく、スキンダイビングやジョギングやサイクリングにも使えるので、ほぼ毎日使っています。使用率ということでいうと、普通のダイコンを買うよりもコスパはいいような気がします。
・残圧計 SUUNTO シリンダー圧計 型番はわかりません。だいぶ古いです
→プラスチック面が割れたので、SUUNTOのSM-36に買い替えました。高圧ホースが細いフレキシブルなものになっていて、軽く使いやすくなっています。
・コンパス SUUNTO 腕に巻きつけるタイプのもので10年くらい前のもの
→ダイコンにコンパスが付いているので、コンパスは持たなくなりました。
・ナイフ TUSA FK11
→変わらず、今も使っています。SCUBAPRO CLASSICのショルダーに固定しています。
・ライト SCUBAPRO NOVA200
→変わらず、使ってます。これは今までのダイブライトで一番長持ちしてます。もう少し光量が強い物がいいけれど大きくなるのは嫌なので、これがベストバランスかなと思います。
・レスキューフロート PADIのプレゼントで当たったもの
→変わらず、同じ物を使っています。
以前書き忘れたり、その後追加した器材。
・ブーツ TUSAの一番安いヤツ
・グローブ SCUBAPROの一番安いヤツ
・ダイビングベル SAS ダイビングベルⅡ
海で死ねるなら本望だと思うんです
ぼくはウォータースポーツをします。スキューバダイビング、シーカヤック、サーフィンをします。
これらのスポーツは事故に遭う危険があり、時には死んでしまうこともあります。
ぼくは35年以上ウォータースポーツをしてきましたが、なんとか今まで死なずにいられました。もちろんヤバイ状況には何度も遭遇しました。
自然を相手にするスポーツですから、事前に入念に準備をし、海にいる間も常に注意を払っていますが、それでも100%安全ということはありません。
ときどき「なぜそんな危ないスポーツをわざわざするのか?」と訊かれることがあります。ぼくからすれば、生きている以上、交通事故とか、ビルの上から物が落ちてきて頭に当たるとか、通り魔に切りつけられるとか、不治の病にかかってしまうとか、そういうリスクはゼロにはならないので、ウォータースポーツをすることで多少そのリスクが上がってもそれは誤差の範囲だと考えています。
そうしたリスクを避けてつまらない人生を過ごすよりも、ウォータースポーツをして自然の中で活動する喜びを味わい、充実した人生を送りたいんです。
海という自然の中でスポーツを楽しむことは、なんともいえな充実感があります。自然との一体感、自然の偉大さ、自身の体力と知力をフルに使ってウォータースポーツを楽しみ、無事に帰ってくるときの達成感と言葉をいくら並べても表現しきれません。こればかりは経験してみないとわからないでしょう。
そんなわけで、ウォータースポーツに出発する際、家を出るときは、妻に挨拶をします。これが最後の挨拶になるかもしれないという思いを込めて挨拶します。そしてウォータースポーツをして、無事に陸上に帰ってこられたときは、強い達成感があります。
海という自然を楽しんでいるのか、単に危険なスポーツをしてスリルを味わいたいのか、自分でもうまく整理できていませせん。
まったく関係のなさそうな話しを書きますが、ぼくが小学生くらいの頃、テレビドラマで「俺たちは天使だ!」というコミカルな探偵ドラマ番組をやっていました。ぼくはそのドラマが好きです。今もDVDをすべて持っていてときどき見かえします。そのドラマの決め台詞に「運が悪けりゃ死ぬだけさ」というものがあるんですが、ぼくはこの言葉も好きです。
そうなんです。ぼくの考え方の根底には、この世に生まれて、しかも障害もなく生まれて、さらに豊かといわれる日本人として生まれて、加えて平均的な家庭に生まれて十分な教育を受けられたのは、運がよかっただけだ、ということがあるような気がします。そして大した病気や事故にも遭わず50歳過ぎまで生きられたのは、運がよかったんだと思うんです。
なので大好きなウォータースポーツをして、海で死んでいけるなら、それは本望だと思います。もともとたまたまラッキーでいただいた命を、自分のライフワークともいえるウォータースポーツをする過程で失うとしても、それは罰当たりなことではないだろうと、ぼくは考えているんです。そして死んだとしても「運が悪けりゃ死ぬだけさ」です。
もちろんせっかくいただいた命と人生ですから、まったく自分の好き勝手に使っていたわけではありません。一応社会人として働いて、社会には、微々たるものですが何らかの貢献をしたようには思いますし、家庭も持ち、子供も自立するまでには育てました。
それらを一応成し遂げた今は、ウォータースポーツを存分にしたいんです。できたら最高の自然を見て、海という自然の中で死んでいきたいとさえ思います。
こんな思いを持ってウォータースポーツをしている人は、あまりいないんじゃないかと推測するんですが、こんな思いを持って海で遊んでいる人が一人でもいるんだということは、誰かに知ってもらいたいと思って、この文章を書きました。
CRC556とCRC666の違いって何?
今回はおもいっきり宣伝みたいになってしまいますが、KURE556でお馴染みの呉工業が作っている潤滑剤について書きます。
海遊びをする人にとっては、身近で便利な製品です。塩ガミ、錆び、何かをスムーズに動かしたいときにはよく使いますよね。
ぼくも、何かと使う機会が多く、いつも常備されている製品のわりにちゃんと使い方を知らないな、って思いました。
呉工業のホームページからいろいろ引用させていただいて、そのあたりをはっきりさせちゃおうと思います。
以前、海遊びをする人には重宝なCRC666っていうのがあるという文章を書きました。
で、CRC556との違いを調べてみると…
【CRC666】
船舶をベストコンディションに保つ、マリーン用の防錆・防湿・潤滑剤
用途
●船舶の電気・電子装置、金属パーツ、マリーンレジャー用品の防錆・防湿・潤滑・保護。
商品説明
●あらゆる船舶の電気・電子部品、船体の金属パーツに防錆・防湿・潤滑性能を発揮します。
●水置換性にすぐれているため金属表面などに付着した水分や湿気を強力に除去します。
●金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐食やサビの発生を防ぎます。
●消防法分類:第3石油類、危険等級III
【CRC556】
用途
●自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
商品説明
●あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の洗浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
●強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
CRC556のQ&Aによると…
Q:5-56にはRoHS指令対象禁止物質は含有されていますか?
A:5-56には鉛およびその化合物、六価クロム化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB(ポリ臭化ビフェニール)類、PBDE(ポリ臭化ジフェニールエーテル)類は含有されておりません。
Q:5-56に固体潤滑剤や研磨剤は含有されていますか?
A:5-56には固体潤滑剤や研磨剤は含有されていません。
Q:5-56にシリコーンオイルは含有されていますか?
A:5-56にはシリコーンオイルは含有されていません。
Q:5-56に塩素系物質は含有されていますか?
A:5-56には塩素系物質は含有されていません。
Q:5-56には有害物質が含まれていますか?
A:毒劇物取締法、PRTR法に該当する有害物質は含まれておりません。
とのことです。
すごくちゃんと納得したわけではないですが、少し納得しました。
これまでどおり、海っぽい用途が多いぼくは、CRC666を使えばいいんだ、っていうのが結論です。
ちなみにこんな文章も書いてますので、もしアレでソレでしたらご覧くださいませ。
→CRC556のPBがカインズで売っている
→ダイビング器材のヒヤリ・ハットをまとめてみました
えーっと今日はこんな感じです。
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
海にいるのが快適な時期ってあります!
海辺の田舎町に住んでいて、休日はほとんど海に出ています。
海のそばに暮らし、海にいることが多いと、海にいるのが気持ちがいい時期があることがわかってきます。それは4月から6月と10月から11月です。もちろんこの時期の毎日が気持ちがいい訳ではありませんけど…
本当に気持ちがいい日って、ぼくの感覚だと年に10日以下だと思います。ぼくは休日しか海に出ていない状況でのこの数字ですから、毎日海に出られる人はもっと多いんじゃないでしょうか。
海にいて気持ちがいい日というのは、太陽がそれほど強すぎず、暑くもなければ寒くもなく、潮風が柔らかく吹いて、湿度が低いんです。なので、朝から夕方までビーチにいても快適です。
偶然にもそんな日にあたると嬉しくなって、なるべく長い時間ビーチにいます。アウトドア用のテーブルとチェアを据え付けて、コーヒーを飲みながら、海を眺め、時に本を読んだりスマホを見たりします。そんな時間を過ごすのって、ぼくとしては最高に価値が高いなって思うんですよね。
こんな風に、日がな一日、海を眺めながら過ごすと、ありきたりな表現ですが、ストレスが解消されて、癒されている実感があります。たぶんヨガやストレッチなどをすると、もっとリフレッシュできるかもしれません。
海にいて気持ちのいい日にあたることが比較的多いのも、きっと海のそばに住んでいて、いつでも海に出られるようにしているからでしょう。
波の種類についてまとめてみました
海辺に住んでいて、海遊びをしていると、波を見ることが多くなります。もちろん水着の女性を見る機会も多くなります。
波にもいろいろな種類がありまして、それを区別する必要がでてきます。
なぜでしょう? なぜかしら?
波をキチンと識別しないと、危険である可能性があるからなのでありますね。
でも、波の表現って、語彙が少ないし、ウォータースポーツごとに違う用語を使ったりして、意外に体系化されていないんじゃないか? 海に囲まれた日本としてそんな状態でいいのか? などなどと思う今日この頃。
それで、ぼくの場合日本語にないけど英語だとうまく表現できそうなものは、英語を借りることにしています。
オジサンになるまで海遊びを続けていると、海に関わる人によって用語が違うことを知ります。漁師さんとウォータースポーツマンでは違う言葉を使いますし、ウォータースポーツによっても違います。
ぼくの場合、それらをゴチャゴチャに使って、一番近い表現を選んでいます。
感覚的にはそうやって波を表現できるのですが、波をキチンと分類しようとすると、とても難しいなあと思いました。理由は、分類の基準によって全然違うからです。
科学的な分類を使うと、実際、海遊びでは使えない大雑把なものですし、それぞれのウォータースポーツで使っている分類を使うと、サーファーには通じても、ダイバーには通じないということが起きます。
きっと誰かがまとめているんだろうなあと思い、検索してみましたが、科学的なまとめはもちろんありますが、あとはサーファーが波の種類を分類しているくらいでした。
ややや、おお、これはどうしたことでしょう。高度に発達したネット社会でこんなことがあるんでしょうか?
というわけで、きっと素晴らしい人頭脳の人がそのうちまとめてくれると思いますが、個人的に知っている現在の知識をまとめてみようかな、いや面倒だからやめとうかなー
【科学的な分類】
●波浪の中に種類がある
まず、基本的な定説として、波(波浪)には風浪とうねりがあります。起きるメカニズムが違うからで、詳しくはこちらをご覧ください。なのだ。
・wikipedia
・All About
通常というか、少なくてもウォータースポーツするうえでは、風浪の方を波と呼び、うねりはうねりと呼ぶことが多いです。風浪なんて言葉を使っている人に未だ会ったことがありません。
このふたつの区別は理にかなったものでして、海にいると明らかに違うとわかります。
波は周期が短く、短時間で様子が変わるものです。うねりは周期が長く、同じような海況が割と長い時間、例えば半日とか1~2日続くことが多いです。
波は岸に近いところでも沖でも同じように立っていますが、うねりは岸に近づくほど、大きく崩れやすく(ブレイクしやすく)なります。逆に沖に行けば、ゆっくり揺られているような感じになります。
サーファーは波を細かく分類して使いますが、彼らはビーチ近くでのブレイクの仕方を分類しているので、実は波とうねりを区別しているわけではなかったりします。でもまあたいていうねりがビーチ近くでブレイクするするほうが、より乗りやすい波であることが多いので、たいていうねりのことをいっています。
●波とうねりに分類してみるとさらに…
○波(風浪)
・ベタまたは凪またはベタ凪 波がなくて鏡のような水面のこと
・さざ波 弱い風で起きる小さな波のこと
・バシャバシャの波あるいはグシャグシャの波 強い風で起きる波ですが、規則性がなく波のトップが風で潰れてしまっている波(このあたりの表現が、すでにサーフィン用語っぽくなっています)
・うさぎが跳ねる波 強い風で沖もうさぎが跳ねているような白波が立っている状態。漁師さんが使います。「ああ今日は沖もうさぎが跳ねてるナー」という感じ。小さな船の漁師さんは海に出ません。
・breaker 砕ける波 この語感にあたる表現は日本語にない気がします。
・ripple さざ波ですが、もう少し大きい感じで、やはり日本語にはないように思います。
○うねり
うねりは大きさで表した方がいい気がします。沖に出て大きなうねりの時は、うねりのボトムとトップでは、大きな船が隠れてしまうほどのときがあります。
うねりはビーチ付近でブレイクしますが、サーファーはこのブレイクした波をいろいろな名前で区別します。
・三角波 うねりがひとつの波長ではなくて、別の波長も含んでいるときに発生します。沖でふたつのうねりがぶつかり合うと、不規則で、ときに大きく、へんてこな形になったりします。うねりの様子を読みにくく、漁船が転覆したりすることもあります。台風や強い低気圧が来ると、気圧の谷を中心に渦を巻くように気圧の等圧線ができますが、そうすると、風の向きが気圧の谷に向かっていろいろな方角から吹きます。そういうときにいろいろな方向からのうねりが起きて、結果的に三角波ができやすくなります。
・swell これも日本語にないのですが、使いやすい言葉です。日本語に訳すと「うねり」だそうですが、もっと大きく周期の長い「海面が隆起する」という感じに近いものがあるような気がしたりしなかったり…
【波やうねりをウォータースポーツごとに分類してみると】
●サーファーの場合
さすがにサーフィンは波で遊ぶスポーツなので波を細かく区別します。
・ダンパー
ダンパーのようにバタンと一斉に崩れる波
・ほれてる波
カールして巻気味の波
・キレてる波
トップからショルダーにかけて順序よくキレイに崩れていく波
・遅い波
パワーがなく、ブレイクするのが遅いか、ブレイクしない波
・速い波
スピードがあって、ブレイクするのが速く、ダンパーに近い波
以上はだいたいうねりがビーチ近くでブレイクする形状を分類したものです。
・バシャバシャの波あるいはグシャグシャの波 先ほども書きましたが、強い風で起きる波で、規則性がなく波のトップが風で潰れてしまっている波
これはいわゆる波(風浪)でして、波っつうのはたいていサーフィンには向かないようです。
●シーカヤッカーの場合
シーカヤッカーは波もうねりも嫌います。それから波よりも風に注意を払うので、波についての区別は少ないといえます。
・ブーマー
波長の長い小さめのうねりの時に、一見穏やかで油断していると、岬の突端など水深が浅いところで、突然大きな波が立つ場所や時があります。それをブーマーといいます。横波を喰らって沈する可能性があるので注意しています。
これはうねりのことをいっていて、しかも特定の地形で起きる現象を捉えています。
●スキューバーダイバーの場合
ダイバーは陸から見た波やうねりの状態から水中の様子を想像するのが特徴です。
女性の服装から推測して身体のラインを思い浮かべるのに…近くないですね…全然…
大きい波やうねりだと海の中がかき混ぜられて、透明度が落ちると判断します。
波長の長いうねりだと水中の透明度が落ちるまではいきませんが、水中でゆらゆらと揺られることを想像します。
それから、ボートダイビングで大きい波やうねりの場合、エントリー・エキジットに苦労するので、ダイビングの中止を考えたりします。ビーチのときも岩場に叩きつけられたりするので、すごく注意します。
波が来る方向も重要です。例えば自分が潜ろうとするポイントが西に向かって開いているとして、西から波が来る場合は、モロに影響を受けますが、東からの波ならば、なんとか潜れるということになります。
というわけで、波とうねり、その大きさ、それが来る方向については注意しますが、それ以上の細かい分類はしません。それよりも海面の様子から潮の流れを知ろうとします。例えば潮目や二枚潮や上げ潮なんかは水面の様子から推測することができることもあります。
●セイラーの場合
セイラーは波やうねりをそれほど気にしません。船が出られるか出られないかというところがポイントです。また船を進める方向は、波やうねりの大きさや向きによって調整します。大きなうねりの場合、うねりに対して船を横に向けると沈しやすくなります。逆にrippleのような波のときにその波に向かって進むとスピードが落ち気味になります。
一方、風は気にします。同じ海域でも風が吹いている場所(ブローがある)と吹いていない場所がありますが、セイラーはブローを探すために、波を手がかりのひとつとします。
というわけで、実際やってみると全然まとまんないですね。
これだとなんだかあれなので、ぼく的に勝手に作っちゃおうかな…
○波(風浪)
・ベタまたは凪またはベタ凪 波がなくて鏡のような水面のこと。ベタベタなんて呼ぶのもあり?
・さざ波 弱い風で起きる小さな波のこと
・ripple さざ波ですが、もう少し大きい感じ
・波あるいはwave 普通の波
・バシャバシャの波あるいはグシャグシャの波 強い風で起きる波ですが、規則性がなく波のトップが風で潰れてしまっている波
・うさぎが跳ねる波 強い風で沖もうさぎが跳ねているような白波が立っている状態。
・breaker 砕ける波
・でかい波 とにかくドーンとでかい波
○うねり
・小者(こもの)のうねり 波長が短く、高低差も小さいうねり。またはAカップのうねりなんて呼ぶのはセクハラ?
・美しいうねり 女性のボディラインのきれいなカーブのうねりを「美しいうねり」とか「ナイスボディのうねり」と呼ぶのはどうでしょう。
・大物のうねり 波長が長く、高低差も大きいうねり
・swell 大物のうねりよりもっと大きく周期の長い「海面が隆起する」という感じのうねり
・三角波 うねりがひとつの波長ではなくて、別の波長も含んでいるときに発生するうねり
うーん、ぜんぜんおもしろくないですね。
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
自分のペースで一日を過ごしたいんです
ノンビリするのが好きです。
用事がないのなら、海に出てウォータースポーツをしたり、海を眺めてボーッとしていたいわけです。
それって怠け者なだけじゃないかというツッコミが聞こえてきそうですが、怠けたいんじゃなくて、というか本音をいうと怠けたいんですが、建前としては自分のペースで一日を過ごしたいんです。自分がやりたいことはたくさんあるので、それを自分のペースでやっていきたいということなんです。本当です。ぼくの目を見てください!
ただ、普通の社会人をやっていると、仕事はやっぱり忙しいし、働き方改革とかいっても、結構残業にになるし、プライベートでもなんだかんだと雑用があります。ぼくが求めているわけではないのに向こうから用事がやって来ます。なんで?
子供の学校の行事とか、親戚の冠婚葬祭とか、友達とか会社の人との飲み会とか、庭の草刈りとか、家電が突然壊れて買いに行かなきゃいけないとか、DMを捨てるとか…そんないろいろなことです。細かなことなんですけど塵も積もれば山となるわけでして…
今は年金暮らしの会社の先輩に聞くと、雑用があるうちが花だといわれましたが、そんなもんかな? 雑用がないならないで、自分がやりたいことはいっぱいあるけどなーと思います。
いや、あの先輩は忙しいのが好きだったからなー、オレはそういうんじゃないからなー、と思ったりします。
カテゴリー
最新記事
(09/20)
(09/14)
(09/13)
(08/31)
(08/30)
(08/24)
(08/23)
(08/17)
(08/16)
(08/10)
(08/09)
(08/03)
(08/02)
(07/27)
(07/20)
(07/19)
(07/13)
(07/12)
(07/06)
(07/05)
(06/29)
(06/28)
(06/22)
(06/21)
(06/15)
最古記事
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
アーカイブ
ブログ内検索
PR
カレンダー
最新コメント
[10/31 TOM]
[06/10 TOM]
[06/10 TOM]
[11/09 porn]
[07/09 和]
PR
google


