海の贈りものを受けとる場所
「海辺で毎日をていねいに大切に暮らしたいな」と思い続けてきました。
海辺の暮らしの中で気づいたこと
海のすばらしさ・楽しさ
ウォータースポーツの楽しさ
などなどをご紹介できたらいいな。
紫外線から身を守れ!
以前DANの会報を読んでいたら、太陽光、特に紫外線による病気に関する記事が載ってました。
ぼくの周りで海遊びしてる人でも何人か目の病気になってるので、改めて気をつけようと思いました。
適度な日光浴は健康のために良いとされている説が多いようなので、この記事は浴び過ぎや無防備な曝露に気をつけようという主旨だと理解しました。
その記事の概略をまとめてみます。
Ⅰ.身体へのダメージ
【熱中症】
これは紫外線というより高温多湿な環境で作業や運動をしたときに起きるものです。熱中症というのは「熱失神」「熱疲労」「熱痙攣」「熱射病」などの症状の総称なんですね。
予防法は、炎天下での激しい運動を避けること、こまめな水分補給です。
具合が悪くなってきたら、風通しのいい日陰に横になり、身体を締めつけるものをゆるめて腋の下など血流のいい場所を冷やすといいようです。霧吹きなどで身体に水をかけます。水分補給は、水を大量に摂るのではなくスポーツドリンクや塩水などの体内の電解質濃度を下げないものがいいようです。
【免疫力の低下】
免疫力の低下はまず肌から起きます。人間の肌の表面には「常在菌」が付着し皮膚を守っているのですが、紫外線にあたりすぎるとそのバランスが崩れて、皮膚の免疫力が低下してヘルペスなどにかかりやすくなります。
皮膚の下には免疫力を司るランゲルハンス細胞があるのですが、これが紫外線によってダメージを受けると、感染症にかかりやすくなるそうです。
夏風邪はその例です。
紫外線の力は通過する大気の距離に反比例しますので、低緯度地域、夏至の時期、昼間が要注意です。
【活性酸素の増加】
活性酸素による身体の老化にも紫外線が関係しています。
通常、体内に酸素を取り入れて食物をエネルギーに変換しているプロセスの中で反応性の高い活性酸素が体内の脂質と結合して「過酸化脂質」を作り、全身のさまざまな細胞にダメージを与えることがあります。これが酸化と呼ばるものです。
活性酸素は紫外線で発生する以外にも、激しいスポーツ、大気汚染、食品添加物・農薬などの化学物質、ストレスなどで発生します。
活性酸素は細胞を錆びさせて老化を促進するだけでなく、ガン細胞を発生させたり、糖尿病を進行させたり、動脈硬化を早めたりすることがわかっているようです。
紫外線の中にはA波・B波・C波があるのですが、特に波長の短いC波は細胞内のDNAを壊し、深刻な疾患を引き起こすようです。
[酸化が発生と進行に関わっている代表的な疾患]
・動脈硬化
・しみ・しわ
・パーキンソン病・アルツハイマー病・筋萎縮性側索硬化症・てんかん
・糖尿病性網膜症・白内障
・気管支喘息・気道障害
・虚血性不整脈・心筋梗塞・高血圧
・急性胃粘膜障害・胃潰瘍・大腸炎・膵炎・脂肪肝
・糖尿病
・癌・アレルギー・リウマチ性疾患・免疫不全・膠原病・後天性免疫不全
Ⅱ.目へのダメージ
【雪目】
海面の光線反射率は90%と高率です。そのため目が受ける影響も大きいといえます。
・角結膜障害は、スキーの際の「雪目」として知られています。ダイビングボートで陽射しの強いときなどは1時間たらずでかかることがあるそうです。炎症を起こしてもすぐに症状が出ず、8~12時間後に目が開けられないほど激しい痛みに見舞われます。痛みを軽減するために冷たいタオルをあてたり、ヒアルロン酸入りの保湿力の高い目薬を注すのが効果的です。
【視覚障害につながる疾患】
以下の病気は紫外線を長期的に浴びると発症率が高まるといわれています。
・瞼裂斑
結膜の変形疾患。白色や黄白色をした三角形の結膜の隆起・肥大で、鼻側にできることが多いようです。異物感があるものの視覚に影響はありません。
・翼状片
結膜の変性ですが、三角形の頂点が角膜に入っていくのが特徴です。進行すると角膜乱視により視機能の低下につながります。
【失明】
・白内障
紫外線による活性酸素の影響で細胞の老化が加速された場合には若年で発症することもあります。放置すると失明にいたる危険性があります。
・加齢黄斑変性症
視野を結ぶ網膜にある要の部位「黄斑」が酸化により変性して失明にいたることもあります。
・結膜にできる悪性腫瘍
【予防法】
若いときから大量の紫外線を浴びることがよくないようです。
帽子、サングラス、ゴーグル、UVカットコンタクトレンズ、防腐剤の入っていない人工涙液目薬、ヒアルロン酸入り目薬などで防御します。
また、ルテイン、ビタミンC・E・A、マルチビタミン、αカロテン、βカロテン、リコピン、オリーブオイルの摂取が効果的との研究データもあるそうです。
Ⅲ.肌へのダメージ
日焼けは「日光性皮膚炎」という病気だそうです。皺やシミの原因にもなります。紫外線を無防備に浴びると光線過敏性皮膚炎や日光じんましんなどアレルギー性の皮膚炎にかかりやすくなるそうです。
日本人の皮膚ガン発症件数は増加傾向ですので注意が必要です。
頭皮や頭髪もダメージを受けて、切れ毛、枝毛、抜け毛につながります。
Ⅳ.全般的な予防法
まず紫外線を浴びないことで、日焼け止め、衣類、日傘、サングラス、帽子を使います。
それから紫外線による身体の中の活性酸素増加を抑えることが効果的なようです。というわけで「抗酸化物質」を摂ることわけですが、抗酸化効果のある栄養素と食物は…
■栄養素
αリポ酸、コエンザイムQ10、ルテイン、ビタミンC・E・A、αカロテン、βカロテン、リコピン、ゼアキサンチン、白金ナノコロイド、ピクノジェノール、アスタキサンチン、オキシカイン、トコトリフェノール、カテキン、ポリフェノール、フラボノイド、プロアントシアニジン、セレン
■食物
ニンジン、ぶどう、トマト、りんご、いわし、鮭、アーモンド、かぼちゃ、ほうれん草、いちご、オリーブオイル、にんにく、ごま、ブロッコリ、メロン、緑茶、ズッキーニ、キィウィ
他にサングラスに関する記事も書いていますので、よろしければどうぞ!
→海遊びをする人のためのサングラスガイド
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
PR
日焼け止めをどう選ぶ?
皮膚の日焼けといえば皮膚がんを連想します。それ以外にも皺やシミの原因にもなりますし、光線過敏性皮膚炎や日光じんましんという病気になることもあるようです。
皮膚を日光に曝さないことが一番でしょうが、そうもいかないときは、日焼け止めの薬ですね。でもどんな日焼け止めを選べばいいんでしょうか?
SPFとPAという指標を参考にするといいようです。
よくCMなんかで聞くこの言葉って実際どういう意味なんでしょうか?
■SPF UVBの防止効果を示す 数値が大きい方が効果は高い
■PA UVAの防止効果を示す PA+、PA++、PA+++で表示し+が多いほど効果が高い
ちなみに紫外線の種類ですが…
■UVB 波長が短い紫外線 皮膚を赤く、水脹れをおこさせ、数日後には、皮膚を黒くさせる作用がある。
■UVA 波長が長い紫外線 太陽光を浴びた直後から皮膚を黒くする作用がある。
⇒日本化粧品工業連合会 『紫外線防止の基本』
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
ダイブコンピュータに搭載されている減圧理論について調べてみました
ダイブコンピュータはレクリエーショナルスキューバダイビングをする際、必須の物になっています。ダイブコンピュータを選ぶ基準はいろいろあるんですが、演算方法もいろいろあるんですよね。ぼくは以前マイクロバブルができにくく配慮した演算方法が搭載されたダイブコンピュータを使っていたんですが、じつはその演算方法がどんなものなのかは理解していませんでした。今回は自分の勉強のために、ダイブコンピュータがどんな理論に基づいて演算をしているのかを、ChatGPTくんに尋ねた結果をまとめてみました。
もしこれを読んでくださっているあなたが、自分のダイブコンピュータがどんな理論で演算しているのか、特徴はどんなところにあるのか把握した上で、ダイビングをされるとより安全なダイビングができるのではないかと思ったりします。
まず、減圧理論の基本と概要をまとめてあるサイトをいくつか紹介します。
●JCUE
次にどんな演算方法があるかですが、現在市販されているダイブコンピュータに使われている理論は、少なくとも以下のタイプがあるようです。もっとあるかもしれません。
VPM-B
ZHL-16C
RGBM
VGM
VVAL-18M
DSAT
DCIEM
それぞれにChatGPTくんの回答を列記します。一部数式などは省略しました。
【VPM-B】
●可変透過性モデル(VPM:Varying Permeability Model、または Variable Permeability Model)は、特定の呼吸ガスを使用する潜水プロファイルにおいて、減圧の計算に用いられるアルゴリズムです。 このモデルは、D.E. Yount らによって、職業的およびレクリエーションダイビング用に開発されました。圧力にさらされた無生物および生体内システムにおける気泡の発生と成長の実験観察をモデル化するために考案され、1986年にはハワイ大学の研究者によって、減圧テーブルの計算にも適用されました。
このアルゴリズムにはいくつかのバリエーションがあり、モバイルやデスクトップ用の潜水計画ソフトウェア、ならびにダイブコンピュータに採用されています。
●理論的基盤
VPMでは、水や水分を含む組織内には常に微細な気泡核(バブルの元)が存在すると仮定しています。そして、潜水中の最大深度(曝露圧)に関連する「臨界サイズ」を超える核は、浮上の際の減圧中に成長します。VPMの目的は、これら成長する気泡の総体積を最小限に抑えることにあり、そのために減圧中の外部圧力を十分に高く保ち、吸入する不活性ガスの分圧を比較的低くするよう調整します。
このモデルは以下の仮定に基づいています:
体内には様々なサイズの気泡核が存在する。
大きい気泡は小さいものよりも成長を始めるために必要な圧力低下が少ない。
そして大きな気泡の数は小さなものより少ない。
これらの仮定により、潜水中に問題を引き起こす前に大きな成長中の気泡を除去するよう設計された減圧スケジュールを提供するアルゴリズムが構築できます。
「可変透過性(Varying Permeability)」とは、気泡を取り囲む分子の層の透過性が状況により変化し、それが気泡内と周囲の間のガス拡散や、圧力変化に対する気泡の圧縮性に影響することを指します。
【ZHL-16C】
●ZHL-16Cは、ダイビングの減圧計算で使用される、アルバート・ビュールマン博士によって開発されたアルゴリズムの一種です。具体的には、ビュールマン博士が1956年から研究を進めた「グラディエント・ファクター」に基づいており、ダイブコンピューターで減圧症のリスクを評価する際に用いられます。
●詳細:
グラディエント・ファクター:
ZHL-16Cは、体内に吸収された窒素が減圧によってどのように排出されるかを予測するモデルです。このモデルでは、窒素の排出速度は、水深や潜水時間、そして体内の窒素濃度分布に依存すると考えられています。
●減圧計算:
ZHL-16Cは、ダイビング中に体内に吸収された窒素の排出状況を予測し、減圧停止を決定する際に重要な役割を果たします。
●ダイブコンピューター:
ZHL-16Cは、ダイブコンピューターに組み込まれており、ダイビング中にリアルタイムで減圧症のリスクを評価し、安全な浮上をサポートします。
●保守性:
ZHL-16Cは、減圧症のリスクを考慮して、安全マージンを設けられています。つまり、減圧停止時間が長めに設定されたり、潜水時間が短く制限されたりする場合があります。
ZHL-16Cは、ダイビングにおける減圧症の予防に重要な役割を果たしているアルゴリズムと言えるでしょう。
ZHL-16Cは、ダイビングで使用する減圧モデルのひとつで、特に減圧計(ダイブコンピューター)や減圧表に組み込まれている減圧理論モデルです。
正式には Bühlmann ZH-L16C と呼ばれ、スイスの医師 Dr. Albert A. Bühlmann が開発した減圧アルゴリズムの改良版のひとつです。
ZH → Zürich (チューリッヒ大学)
L → "Limit"(限界)
16 → 16の仮想組織コンパートメントを使用
C → バージョンC(A→B→Cと進化した3つ目)
●基本の考え方:減圧理論の基礎
ダイバーが水中に潜ると、呼吸ガスに含まれる窒素(N₂)が体の組織に溶け込んでいきます。浮上時に急激に圧力が下がると、溶けていた窒素が気泡となってしまい、これが**減圧症(DCS)**の原因になります。
このため、浮上速度や減圧停止を適切に設定する必要があり、その指標となるのが減圧モデルです。
●ZHL-16Cの特徴と理論的な根拠
16の組織コンパートメント
人間の体を**窒素の吸収・排出速度の異なる16の仮想組織(コンパートメント)**に分けて考えます。
例えば:
1番:血液・脳など早い組織(ハーフタイム 4分)
16番:脂肪組織など遅い組織(ハーフタイム 635分)
●ハーフタイム(T₁/₂)
それぞれの組織で、吸収・排出する窒素量が半分になるのにかかる時間。
→ これにより、組織ごとに異なる窒素分圧の変化を計算。
●M値(M-value)
そのコンパートメントが耐えられる最大の許容窒素圧(=減圧限界)
→ 組織ごとに設定されたM値を超えないように浮上・減圧停止を計画。
●ZHL-16A・B・Cの違いは?
バージョン 特徴 用途例
ZHL-16A 初期版。保守的 医療・研究目的
ZHL-16B より現実的なM値を設定 スポーツ・レクリエーショナル
ZHL-16C 安全マージンを改善し現代的な運用に適合 最新のダイブコンピューター搭載
●なぜZHL-16Cが多く採用されるのか?
・多様なダイブプロファイルに対応できる
・実績・データが豊富で信頼性が高い
・ダイブコンピューターでリアルタイム計算が可能
・Gradient Factor(安全係数のカスタマイズ)との相性も良い
【RGBM】
RGBM(Reduced Gradient Bubble Model)は、アメリカの物理学者Dr. Bruce Wienkeが開発した減圧モデル。
Bühlmann(ZHL)などの古典モデルが「溶解ガス理論」に基づくのに対し、RGBMはそれに「気泡動力学」を組み合わせたハイブリッドモデル**。
つまり:
体内に溶け込んだ窒素の挙動と
減圧中に発生する気泡のサイズと数、成長・縮小の過程
の両方を数値モデル化して浮上計画を立てます。
●理論的な根拠と基本構造
・ RGBMの基本前提
すべてのダイビングでマイクロバブル(微細な気泡)は発生する減圧症(DCS)は、溶解ガスの過飽和+気泡の成長によって引き起こされる
よって、減圧モデルには溶解ガス動態+気泡動態の両方を組み込むべき
●気泡動力学の理論
・ マイクロバブルの考え方
ダイビング中、体内に微小なガスの核(bubble seeds)が常に存在し、浮上・減圧中にこれらが成長・崩壊・再吸収する。
RGBMは、この核の成長を抑えつつ浮上するプロファイルを計算することで、DCSリスクを軽減。
●RGBMの数理モデルの仕組み
以下の要素を組み合わせて減圧計算を行います。
要素 内容
ガス溶解方程式 ZHLなどと同様の組織コンパートメントを使用し、溶解ガス量を計算
気泡拡散方程式 気泡内外のガス分圧差による気泡の膨張・収縮をモデル化
再膨張制限 気泡が再膨張しないよう、浮上速度や減圧停止を厳しく設定
連続潜水・反復潜水の累積効果 体内の未排出マイクロバブルの残存を考慮
●ZHLとの違い
項目 ZHL (Bühlmann) RGBM
基本理論 溶解ガス理論のみ 溶解ガス理論+気泡動力学
減圧計算 コンパートメントの過飽和限界(M値)のみ マイクロバブルの成長・収縮も考慮
浮上・減圧停止の特徴 シンプルで自由度高い 浮上速度制限が厳しく、追加の減圧停止が入ることも
反復潜水の管理 溶存ガスの残留量のみ マイクロバブルの残存も考慮
●RGBMのメリット・デメリット
・ メリット
マイクロバブルを抑制し、DCSリスクを低減
特に反復潜水・ディープダイブ・減圧潜水で効果的
実績豊富で、多くのダイブコンピューターに搭載
・ デメリット
浮上速度や減圧停止が保守的になりがち(ZHLより停止が多いことも)
理論が複雑で、ダイブテーブル化が難しい(ダイブコンピューター向き)
【VGM】
●基本構造
VGMは基本的にはZHL(Bühlmann)ベースの減圧モデルを元にしていますが、そこにダイビング中の条件に応じてM値(限界圧力差)をリアルタイムに動かす補正関数を加えます。
●背景理論
人間の体は静的な環境ではない
→ 同じ深度・同じ時間でも、前回の潜水履歴・ダイバーの状態・浮上速度によってDCSリスクは異なる。
従来の固定M値では現実の潜水条件を十分にカバーできない
→ より現実的な動的管理が求められる。
Gradient Factorの発展型
→ Gradient Factor (GF)は、あらかじめ設定された高圧時と低圧時のM値割合を制御するのに対し、
VGMはその設定すらダイブプロファイルに応じてダイブ中に変化させる。
●VGMの特徴と効果
特徴 内容
動的M値 ダイブプロファイルに応じてM値を常に変動
より現実的な減圧計画が可能 実際の潜水状況・履歴・浮上速度などの影響を直接減圧停止に反映
反復潜水・ディープ潜水に強い 前回のダイブ履歴からM値を調整し、DCSリスクの蓄積を適切に管理
従来モデルより安全マージンを確保 特に浮上速度超過・急浮上後などのリスク状況でも自動で停止を追加調整
●VGM搭載の実例
最近のハイエンドダイブコンピューターにVGM系統のアルゴリズムを採用する例が増えており、特に
Shearwater
Ratio
Scubaproの新型
などで動的減圧モデルの採用例が報告されています。
正式に「VGM」と銘打たれてないこともありますが、実質この機構を取り入れてるモデルも多いです。
●まとめ
・VGMは従来のZHLの「固定M値」の欠点を克服し、ダイブ中の状況や履歴に応じてM値を可変化させる減圧モデル
・特に反復潜水やディープダイブ、緊急浮上時の安全性向上に寄与
・数値モデルはZHL+動的補正式で実装し、最新ダイブコンピューターで採用例増加中
【VVAL-18M】
VVAL-18Mの理論的背景
1. Exponential–Linear(指数–線形)モデル
VVAL-18Mは、従来のホールデンモデル(Haldane Model)を基にしつつ、ガスの吸収(インガス)と放出(アウトガス)の速度を異なる関数で表現しています。具体的には、組織へのガスの吸収は指数関数的に、放出は線形関数的にモデル化されています。このアプローチにより、特に減圧時のガス放出が遅くなる深度域でのリスクをより正確に評価できます。
2.多組織コンパートメントモデル
VVAL-18Mは、異なる半飽和時間を持つ複数の組織コンパートメントを使用して、体内のガス挙動をシミュレートします。これにより、短時間でガスを吸収・放出する組織から、長時間かけてガスを処理する組織まで、幅広い生理的反応をカバーしています。
3.M値(Maximum Allowable Tissue Tension)
各組織コンパートメントには、許容される最大のガス分圧(M値)が設定されています。減圧中にこのM値を超えないようにすることで、気泡の形成を防ぎ、減圧症のリスクを低減します。
実用化と検証
VVAL-18Mは、米海軍のダイビングマニュアル(Revision 6および7)に基づく減圧テーブルの作成に使用されています。また、閉回路リブリーザー(CCR)や混合ガス潜水など、特定の潜水環境においても適用されています。このアルゴリズムは、実際の潜水データや実験結果を基に検証されており、減圧症の発症率を3.5%未満に抑えることが期待されています 。
他の減圧モデルとの比較
VVAL-18Mは、ビュールマンモデル(ZHL-16)などの他の減圧モデルと比較して、特に深度のある潜水や長時間の潜水において、より保守的な減圧プロファイルを提供する傾向があります。これは、減圧症のリスクをさらに低減するための設計によるものです。
まとめ
VVAL-18Mは、指数–線形モデル、多組織コンパートメント、M値の概念を組み合わせた高度な減圧理論であり、特に高リスクの潜水環境において、安全かつ効率的な減圧を実現するために設計されています。その理論的根拠と実用性から、米海軍をはじめとする多くのプロフェッショナルダイバーに採用されています。
【DSAT】
●DSATの理論的な根拠
1.ビュールマンZHL-16の応用と調整
DSATモデルのベースはスイスのハンス・ビュールマン博士が開発した**ZHL-16(16コンパートメントの多組織コンパートメントモデル)です。
体内の異なる組織を半飽和時間の違いによる16種類の「コンパートメント」**に分け、それぞれのガス吸収と排出を指数関数で表します。
2.レクリエーションダイビング向けの安全係数
レクリエーショナルダイビングでは、テクニカルダイビングや軍用と違い意図的な減圧停止を行わず、水面への直接浮上を原則とするため、
ビュールマンモデルに比べてさらに**保守的なM値(最大許容組織内不活性ガス圧)**が設定されています。
特に浮上速度や「ノーストップタイム(無減圧潜水時間)」に対して厳しい制限を設け、
万が一浮上速度が速くなっても気泡の形成リスクを抑えるように設計されているのが特徴です。
3.指数関数モデルとM値設定
減圧理論の基本である、
**「組織のガス吸収・排出=指数関数的に進行する」**という考え方に基づき、
それぞれの組織に対し、浮上時に許容できる最大組織内ガス分圧(M値)を定め、
減圧症のリスクを数値的に管理します。
DSATでは、ZHL-16のM値を基にして、レクリエーション用としてより低いM値を設定し、短時間での水面浮上に耐えうるように調整。
4.大量の実潜データと統計解析
開発時にPADI DSATリサーチチームは、数千ダイブ分の実潜データを取得し、
統計学的に減圧症発症率との相関を解析。
その結果、無減圧潜水の限界時間や安全停止ルール(3分 at 5m)などが確立されました。
●まとめ
DSATモデルは
・ビュールマンモデルをベースに
・レクリエーションダイビング向けに安全側へ調整し
・実潜データと統計解析で安全性を検証した減圧理論
といえます。
特に「意図しない減圧停止」を前提としないダイビングのために設計されており、浮上速度や安全停止のルールもこのモデルに基づいています。
【DCIEM】
●DCIEMの理論的な根拠
1.溶解ガス理論(Haldaneanモデル)
やはり基本はここ。
複数の仮想組織コンパートメント(通常8~10個)にガスの吸収と排出を計算する溶解ガスモデル。
ハーフタイムは5分~750分と幅広く、急速・中速・遅い組織の挙動をシミュレーション。
2.実験データに基づく発症確率モデル
DCIEMの革新的な部分。
実験潜水で得たDCS発症データと気泡発生データを用いて、以下の条件ごとにDCS発症リスクを統計的に解析。
ダイブ深度
潜水時間
浮上速度
減圧停止時間と深度
気泡の超音波検出データ
これにより、
許容される組織過飽和圧(M値)
必要な減圧停止プロファイル
を単なる理論値でなく実験でDCSが起きなかった安全域で設定。
3.気泡動力学的影響の統計的考慮
RGBMのように個別気泡の成長計算はしないが、
実験時の気泡検出データ(Doppler超音波)を統計的に解析し、DCS発症と相関する条件を特定
この結果を基に
気泡発生が多かったプロファイル → 保守的に設定
気泡発生が少なく、発症例もなかったプロファイル → 安全域とする
という統計ベースの気泡リスク管理を行う。
●DCIEMの特徴まとめ
項目 内容
コンパートメント数 8~10
気泡動力学の考慮 超音波気泡データの統計的解析による間接的考慮
減圧停止 実験データから安全停止パターンを設定
無減圧潜水限界の設定(NDL) 実験データに基づく保守的設定
減圧症発症率の基準 実験潜水の発症率・気泡検出状況で統計的安全域を決定
●採用実績と用途
・カナダ海軍ダイブテーブル
・商業ダイビング会社(SAT・長時間減圧)
鳥のさえずり・リスの鳴き声・木々の葉音
我が家は海辺にあるんですが、たまたま家の後ろが小高い山というか丘になっていて、まあ森といっていいくらいに木々が生えています。そんな立地なので、様々な種類の鳥(ぼくが鳥の種類を見分けられないのでよくわからないんです)がいたり、リスがいたり、タヌキがいたりします。もしかしたらもっと他の動物もいるのかもしれません。
幸いなことに獣害というような目には遭っていません。たまにぼくが植えたミカンの木の、ミカンの実をリスに食べられるくらいです。せっかくマーマレードにしようと思っていたのに…
ぼくはエアコンが好きではなくて、というか締め切った空間にいるのが好きではなくて、季節ごとにできる限り窓を開けておきたいんですが、窓を開けていると、いろいろな自然の音が聞こえます。
鳥の種類もわからないぼくですが、鳥のさえずりを聞いたり、リスの鳴き声を聞いたり、風が吹いたときの木々の葉が擦れる音を聞くのは好きです。風の強い日は、波の音も聞こえます。
自然の発する音というのは、ぼくにとってはうるさく感じないんですよね。むしろ心地よくて、癒されます。
そんな自然の音に耳を傾けていると、あっという間に時間が過ぎています。でもそれはとても好きな時間の過ごし方なんです。
こんな短パンなら海遊びも快適!
まだまだ厚日が続いていますね。
とはいえぼくは短パンバカなので、冬でない限りできるだけ短パンを穿いています。短パンだと動きやすいし、足にまとわりつかないから、いい歳して秋口でも短パンを穿いてしまいます。
ところでぼくはウォータースポーツはいろいろやるので、道具にもある程度、気をつけているんですが、知らないうちに短パンが随分使いやすくなっているみたいです。
高機能な素材でできた短パンが出てきていて、快適性が増しているようです。
道具にあまりこだわりすぎるのもどうかと思うんですが、ダイビングにしろ、シーカヤックにしろ、道具によって快適さってすごく違うんですよね。
日々身に着ける短パンが快適なものだと、毎日も過ごしやすいし、海遊びの時も楽しいですよ。
というわけで、海で使う短パンの体験談をまとめてみますが、まずぼくの短パン選びの基準から…
【短パン選びの基準】
1.撥水性の高い素材を使っている
2.股の部分にライナーがついている
3.ポケットは最小限で、裏地はメッシュの面積が大きい
4.すぐ乾く素材でできている
【これまで使った短パン比較】
■スェット地の短パン

これは綿100%の、スエットの生地の短パンです。生地が厚くて水を吸うので、濡れると重くなって、ズリさがってきます。
それに乾きが、すごーく悪いですねえ。
こういう短パンで海辺に近寄らないほうがいいです。
ただ、タオルみたいで着心地がいいので、部屋着とか散歩用にはいいかもね。
■Helly Hansenの短パン

綿70%、ポリエステル30%です。生地が薄くて、あまり水を吸いません。乾きもまあまあ。
これは10年くらい前に買ったものなので、そんなに高度な素材を使っていないかもしれません。でも耐久性という意味ではすごくいいですね。
あえて難点を探せば、ウエストを調節するひもが綿でできていて、これの乾きが良くなくて、濡れたひもが腹にあたって少し違和感があったりします。
その後、このひもを、ディンギーなんかで使う水を吸わないロープに替えました。

バックポケットには水が抜ける穴があります。でもそもそもバックポケットがいらないと思います。
写真には写っていませんが、ポケットの入り口にベルクロのファスナーがついていて、ポケットの物が落ちないようになっています。

フロントポケットの裏地はメッシュで、濡れても水が落ちるようになっています。
■CANTERBURYの短パン

素材はポリエステル100%です。
生地が薄くて、とにかく軽いです。着心地もいい。ポリエステルだからといって、蒸れたりしません。
驚くのは、濡れても、汗をかいてもすぐに乾きます。
フロントポケットの入り口にはベルクロのファスナーがついていて、ポケットの物が落ちないようになっています。
ウエストのひもの乾きもgood!
たぶん海で使う目的ではなくて、陸のスポーツで使うことを目的として作られているためだと思うんですが、ライナーがついていません。残念!
■patagoniaの短パン

外側はナイロン100%、ライナーはポリエステル100%です。
表地には撥水加工がしてあり、水をはじきます。
生地も薄く、CANTERBURYほどではないけれど軽いです。
この短パンも乾きやすいし、ウエストのひもの乾きも良いです。

ライナーがあると、濡れて生地が湿っていても、それが肌にまとわりつかなくて、着心地がいいです。
ほぼ海パンとして使えます。

フロントポケットの裏地の下の部分がメッシュになって、水が抜けるようになっています。
でも、もう少しメッシュの部分の面積が大きいほうが水の抜けが良くていいと思います。それからメッシュの目が細かすぎて、洗濯の時ポケットに入った砂を取るのがメンドウです。
■モンベルの短パン

外側はナイロン100%、ライナーはポリエステル100%です。
生地には撥水加工がしてあります。
この短パンも使いやすいですね。

後ろの腰の部分がメッシュになっていて、短パンに入った空気が抜けるようになっています。よく水の中で短パンに空気がたまって風船のようになったりしますが、この短パンだとそういうことがありません。なかなかよく考えてあります。

これも股にライナーがあります。

ポケットの裏地のメッシュの面積も大きくていいですね。
どうでしょうか? 短パンを選ぶとき少しは参考になるかな?
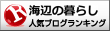
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
とはいえぼくは短パンバカなので、冬でない限りできるだけ短パンを穿いています。短パンだと動きやすいし、足にまとわりつかないから、いい歳して秋口でも短パンを穿いてしまいます。
ところでぼくはウォータースポーツはいろいろやるので、道具にもある程度、気をつけているんですが、知らないうちに短パンが随分使いやすくなっているみたいです。
高機能な素材でできた短パンが出てきていて、快適性が増しているようです。
道具にあまりこだわりすぎるのもどうかと思うんですが、ダイビングにしろ、シーカヤックにしろ、道具によって快適さってすごく違うんですよね。
日々身に着ける短パンが快適なものだと、毎日も過ごしやすいし、海遊びの時も楽しいですよ。
というわけで、海で使う短パンの体験談をまとめてみますが、まずぼくの短パン選びの基準から…
【短パン選びの基準】
1.撥水性の高い素材を使っている
2.股の部分にライナーがついている
3.ポケットは最小限で、裏地はメッシュの面積が大きい
4.すぐ乾く素材でできている
【これまで使った短パン比較】
■スェット地の短パン
これは綿100%の、スエットの生地の短パンです。生地が厚くて水を吸うので、濡れると重くなって、ズリさがってきます。
それに乾きが、すごーく悪いですねえ。
こういう短パンで海辺に近寄らないほうがいいです。
ただ、タオルみたいで着心地がいいので、部屋着とか散歩用にはいいかもね。
■Helly Hansenの短パン
綿70%、ポリエステル30%です。生地が薄くて、あまり水を吸いません。乾きもまあまあ。
これは10年くらい前に買ったものなので、そんなに高度な素材を使っていないかもしれません。でも耐久性という意味ではすごくいいですね。
あえて難点を探せば、ウエストを調節するひもが綿でできていて、これの乾きが良くなくて、濡れたひもが腹にあたって少し違和感があったりします。
その後、このひもを、ディンギーなんかで使う水を吸わないロープに替えました。
バックポケットには水が抜ける穴があります。でもそもそもバックポケットがいらないと思います。
写真には写っていませんが、ポケットの入り口にベルクロのファスナーがついていて、ポケットの物が落ちないようになっています。
フロントポケットの裏地はメッシュで、濡れても水が落ちるようになっています。
■CANTERBURYの短パン
素材はポリエステル100%です。
生地が薄くて、とにかく軽いです。着心地もいい。ポリエステルだからといって、蒸れたりしません。
驚くのは、濡れても、汗をかいてもすぐに乾きます。
フロントポケットの入り口にはベルクロのファスナーがついていて、ポケットの物が落ちないようになっています。
ウエストのひもの乾きもgood!
たぶん海で使う目的ではなくて、陸のスポーツで使うことを目的として作られているためだと思うんですが、ライナーがついていません。残念!
■patagoniaの短パン
外側はナイロン100%、ライナーはポリエステル100%です。
表地には撥水加工がしてあり、水をはじきます。
生地も薄く、CANTERBURYほどではないけれど軽いです。
この短パンも乾きやすいし、ウエストのひもの乾きも良いです。
ライナーがあると、濡れて生地が湿っていても、それが肌にまとわりつかなくて、着心地がいいです。
ほぼ海パンとして使えます。
フロントポケットの裏地の下の部分がメッシュになって、水が抜けるようになっています。
でも、もう少しメッシュの部分の面積が大きいほうが水の抜けが良くていいと思います。それからメッシュの目が細かすぎて、洗濯の時ポケットに入った砂を取るのがメンドウです。
■モンベルの短パン
外側はナイロン100%、ライナーはポリエステル100%です。
生地には撥水加工がしてあります。
この短パンも使いやすいですね。
後ろの腰の部分がメッシュになっていて、短パンに入った空気が抜けるようになっています。よく水の中で短パンに空気がたまって風船のようになったりしますが、この短パンだとそういうことがありません。なかなかよく考えてあります。
これも股にライナーがあります。
ポケットの裏地のメッシュの面積も大きくていいですね。
どうでしょうか? 短パンを選ぶとき少しは参考になるかな?
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
初夏の海の気持ちよさ
初夏の海って気持ちいいんです。特に早朝がいいですね。5時とか6時とか…早すぎますか?
空気は澄みきっていて、砂浜は、その日まだ誰も立ち入っていない感じで、フレッシュな気がします。
初夏の早朝の海辺は、まだ気温が上がっていなくて涼しいくらいです。気象条件の関係で霧が出る日もあります。霧の中を砂浜を散歩するのは、ちょっと幻想的でワクワクします。なんだか別な世界に足を踏み入れたような感じがします。
真夏の7月8月になるとこの砂浜は、観光客のものになります。地元の人は、家でひっそりと自分たちの時間を楽しむか、高原や海外の涼しいところへ旅行に行きます。
湘南に関所を作ったら? 大人のための落ち着いた観光地があってもいいのでは? そのために入域税などとったらどうでしょうか?
ぼくは相模湾に面した首都近郊の海辺の町に住んでいます。
なのでというか、なのにちゅうか、土日や夏休みは観光客が来る土地です。最近はインバウンドで外国人観光客の人も多く見かけるようになりました。
ぼくも他所の海へ遊びに行くので、そういう時はぼくが観光客になります。で、やはりそういう時は楽しいわけで、いつも以上にはしゃいだりします。
自分が観光地に住むようになって感じるのは、そういう観光客の人達を見るのは複雑な気持ちということです。
複雑な気持ちというのは、来てくれて嬉しいという気持ちと、自分達の住んでいる土地で騒がれてちょっと迷惑という気持ちが入り混じっている状態なのですね。
たいていの観光地は観光も地場の主要な産業なので、観光客誘致を積極的に進めています。たとえ自分が直接観光産業に携わっていなくても、地域全体の経済が活性化することは歓迎すべきことでしょう。
ただ、ぼくの場合、地元の産業とは関係なく収入を得ているのです。
なので、観光産業が盛んになってもならなくても、直接は関係ありません。もちろん地元がさびれれば、その分、町の財政も逼迫し、税金や行政サービスなどの面で負の影響を受ける可能性はありますが…
で、個人的な思いをすごく単純にいうと観光客が来てもメリットはあまりないけど、騒がしかったり、道路が渋滞したり、治安が悪くなったり、ビーチが混雑したり、町やビーチにゴミが散乱したりとデメリットの方が多いんです。
たとえば地元の人というのは、普段スーパーやコンビニに行くにも車なんですが、まあ割とゆっくり走るんです。田舎町ですからノンビリしていて生活のスピード自体が遅いのと、高齢化しているのでお年寄りがたくさん運転しているわけです。それで、車のスピードが全体的に遅いと。
んで、観光客の若者とかが道路をかなり飛ばして走るわけです。
たまにそういう車に煽られたりして危ないんですね。
それってどうなんだ!と思うわけです。
もうひとつの例として、観光客が海の家とかビーチで酒を飲むでしょう。いや、それ自体はいいんですけど、そういう人達の中にはからんだり、喧嘩したり、まあ軽犯罪みたいなことをする人もいるわけです。
で、地元の年頃の娘さんがいる家などはかなり用心するんですね。最近いろいろ物騒な事件が多いですから…
ぼくの家などはちょっと前まで家も車も鍵をかけなかったですが、最近はちゃんと戸締まりします(当たり前かなー)。
周囲の人やあるいは離れた場所ですけど茅ヶ崎とか藤沢の友人なんかも似たような感想だったりします。
どちらかというと、ぼくの体験よりもすごくて、深夜の花火がうるさい、海の家の音楽がうるさい、暴走族がうるさい、家の前のガレージに無断で駐車された、家の前にゴミを捨てられた、洗濯物が盗まれた、庭のサーフボードが盗まれた、店の品物を万引きされた、からまれて喧嘩になった、などなどかなり迷惑を受けている様子なんです。
まあもっと乱暴にいうと、あまりお育ちの良くない観光客の方達が来て、不作法なことをして、地元の人は眉をひそめていると…んで、そういう人達ってどうせ大してお金を落とさないんじゃないの?ということなのです。
で、たとえば茅ヶ崎とか藤沢なんて、観光産業というよりも大企業の工場とかサラリーマンなどの税収の方がたぶん多いでしょうから、別に観光客が来なくてもいいんじゃないかと思ったりするわけです。
ここまでかなり地元民的な偏った内容かもしれませんが、今回はこのまま突っ走ろうと思います。
そいでね、ここからかなりラディカルになってしまうわけですが、日本の観光地というか地方のすべてが観光客歓迎、観光産業振興一直線でなくてもいいんじゃないか?と思うんです。
日本の…なんて大きな話をするとわけがわからなくなってしまうんで、とりあえず、湘南あたりの別に観光客が来なくても財政的に致命的にならない地域などは、他所の人がエリア内に入るときは、入場税をとったらどうなのか?と思ったりするわけです。
鎌倉とか茅ヶ崎とかの134号線に関所を作ったりしてね。
というのもフロリダを旅行したときには、入域税を払った記憶があるんですけど、あれと同じことをしたらどうでしょう?って思ったりするんですね。
何かの法律に抵触するかもしれませんけどね…
これはあまりにも排他的、非リベラルな考え方かもしれませんね。もう少しオープンで自由であってもいいかもしれません。
まあ、もうちょっとビジネスライクに考えるとして、逆に自分が観光客だとしてですね、たとえばそうですねえ、軽井沢のような避暑地に行って、旧軽なんて夏はすごく混雑してますでしょ、そんな中を樹木の名前も搾りたての牛乳の味もわからなそうな若者が歩いていたりするとウンザリするんですよね、上から目線ですけど…
だったら入域税を払ってでも一定の層が来ている落ち着いた観光地に行きたいですね、ぼくは。そういうところでゆったり落ち着いた気分で過ごしたいです。
つまりですね、いい方を変えると、良識ある大人がゆったり過ごせるハイソな観光地というのは、それはそれで売りになるのではないのかなあーと思ったりしている今日この頃です。
みなさんいかがお過ごしでしょうか。黒柳徹子です。
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
ぼくがシーカヤックを始めたきっかけ・そしてその魅力
ぼくがシーカヤックを始めたのは1990年代の後半のことでした。それまではスキューバダイビングとサーフィンをやっていました。
で、あるとき海でシーカヤックをやっている人を見かけて、面白そうだなと思って、すぐに家の近くのシーカヤックアウトフィッター(シーカヤック業界ではシーカヤックのスクールやガイドをしている店をアウトフィッターと呼びます)でシーカヤックをレンタルで貸してもらって、1日体験しました。このあたりの海遊びに関するぼくの行動力は、我ながら驚くほど迅速です。
シーカヤックを体験した感想は「これは面白い」「かっこいい」「シーカヤックの船体は造形的に美しい」「とても自由」というものでした。
というわけで、これも早速、シーカヤックを一艇買いました。30万円くらいして、ぼくの買い物としては高かったわけですが、そこは思い切って買ってしまいました。
都合のいいことにぼくの家は海まで徒歩3分で、海まで階段も大きな段差もなく、シーカヤック運搬用のカートにシーカヤックを積んで、コロコロ引っ張りながらビーチまで行けたのです。
シーカヤックを保管する場所もガレージの隅が空いていたので、そこに置くことができました。
そんなわけで、休日の海が穏やかな日はシーカヤックをすることが多くなりました。たいていのことがそうだと思うんですが、慣れて上達して要領がよくなるほど、楽しくなってハマっていくものです。
ぼくはシーカヤックの自由さに魅了されました。セイリングほど艤装に時間がかからず、モーターボートのように水深や機器のことに気を使わずに使えます。
とにかく身軽で自由にいろいろなところへ行けます。
特にぼくがハマったのは、海からしかアクセスできない砂浜や岩場にシーカヤックで行って、キャンプをするということです。ぼくだけしかいないビーチにテントを張って、ノンビリ1泊2日の一人旅を楽しむ行為は「自由」という言葉がピッタリです。
キャンプは以前からやっていたんですが、ぼくはキャンプ場というのが嫌いなんです。シャワーがあって温水暖房便座付きの水洗トイレがあって、決まった区画で、お隣さんに迷惑をかけないように静かにキャンプするというのがなんとも息苦しくて、まったく自然な感じがしなくて苦手だったんです。でも今の日本でキャンプしようとすると、キャンプ場へ行くしかありません。それ以外の場所でキャンプしていると、近所の人や警察や自治体の人から注意されます。
自然の中で屋外で寝泊まりはしたいし、焚き火もしたいというぼくは嫌々ながらキャンプ場へ行っていたんです。
そんな悶々としたぼくのキャンプ生活を、シーカヤックは変えてくれたんです。
シーカヤックに乗るようになってからは、腕の筋肉はもちろん、背筋や腹筋や足の筋肉も付き、身体が締まった気がします。シーカヤックは腕だけで漕ぐと思っていたんですが、全身の筋肉を使うんですね。
そして何より広大な海の上を、ポツンと自分の力だけで移動していく爽快感はたまりません。ときには朝日を、ときには夕陽を眺めながら、青い海の上を漕いでいくんです。それは気持ちいいものです。
シーカヤックを始めてからは、ぼくのウォータースポーツライフは、海況がよくて魚が見られる頃にはスキューバダイビングを中心にやります。それ以外の休日で、海が穏やかならばシーカヤック、いい波があればサーフィンをします。海が荒れ荒れでどうしようもないときは、海辺を散歩、という感じの組み立てになりました。
休日で何も用事が入っていない日というのは、実はそれほど多くないわけですが、何も用事がない日は全力で海遊びをします。そうすると平日の仕事で溜まったストレスが、スッと身体から抜けていく感じがします。
ぼくは今50代ですので、体力を維持しながら、できる限り長く、ウォータースポーツを楽しみたいなと思っています。
海遊びをする人のためのサングラスガイド
【海遊びにはサングラスはとても大切】
みなさん海遊びしてますかー?
今回は海で使うサングラスの話などいかがでしょうか?
えっ!今は冬だ?
いやいや冬でも1日海にいると日焼けしますよ。
それでもちろん目も日焼けしちゃうんですね。
特に最近は、オゾン層の破壊で紫外線が強くなっているような気がします。気のせいかな?
ぼくの知り合いのサーファーで、もう50歳くらいの人なんですけど、陽にあたりすぎちゃって、目が悪くなってしまって、医者に「陽の強いところに行かないように、サングラス必携」といわれたそうです。
いやー明日はわが身か・・・気をつけないといかんですね。
ここまで悪くなる前にサングラスをして目を保護しないと…
サングラスはオシャレでかけるという面もあるけど、やっぱり、大切なのは目の保護ということですね。
で、そういう目的だとすると、海遊び人が選ぶサングラスは、ハリウッドのスターの間で今、流行中とかいうのとは違うわけです。
はっきりいって大切な機能は、UV、えーっと紫外線をカットすることです。紫外線カット率!
その次に使いやすいのは、特にマリンスポーツをする人は、激しく動いてもズレたり、落ちたりしないものです。
しかしすごいですね。この間マリングッズを売ってる店で見つけたんですが、水に落ちても沈まないサングラスというのがありました。これなんかディンギーやシーカヤックをやる人はいいんじゃないでしょうか。
これは海遊び人、特に釣り好きな人はご存知だと思うんですが、偏光グラスというのがあって、これだと水面のギラツキが気にならなくて、ちょっとした浅瀬の岩場なんかはよく見えます。
あとサングラスの効用で忘れていけないのは、目にごみがはいりにくいというところです。風の強い日に海辺にいるとどうしても砂が目に入ってくるんです。サングラスをかけていると砂が目に入りにくいんですね。これは砂に限らず花粉についても同じです。花粉症の方はサングラスが役に立ちます。
【サングラスの選びのポイント】
それでですね。ぼくのサングラス選びなんですが…
■色の濃さ
まず気をつけるのは色の濃さですね。
ブラックでもブラウンでもグレーでも色の濃さがあって、色が濃いほど、眩しくないわけです。でもですね、陽射しが弱いときは、あまり色の濃いグラスだと、暗くて見えにくいんです。
ぼくの場合は、不精でして、陽射しによって、頻繁にサングラスをかけたりはずしたりするのは面倒なので、あまり濃い色のグラスは選びません。
■UVカット率
2番目は、UVカット率ですが、これはもう今は100%とか97%が当たり前です。
■偏光グラス
3番目なんですが、これは偏光グラスにするか普通のグラスにするか、これは用途によるんですが、海遊びをするんなら偏光グラスを選んでおいた方が用途が広いと思います。
あとはね、水に浮くとか、デザインがナイス!だとか、そういう自分の好みで選ぶんですね。
【どんなメーカーがあるの?】
ちなみにぼくが何個か使ってみて良かったのはOAKLEYのサングラスですね。レンズのバリエーションがいっぱいあって選べるのと、激しい動きをしてもずり落ちにくいところがいいですね。それになんかカッチョイイですね。ちなみに知り合いのヨット乗りの人が「HALF WIRE」をかけてて、なかなかイケてました。
OAKLEYの場合、テンプル(耳にかかる部分)の部分が少し内側に傾いてついています。弾力があるので多少外側に引っ張っても大丈夫です。この弾力でずり落ちないようにしています。ぼくの友人で頭の大きい人がいるんですが、OAKLEYを長くかけていると、つるが当たるところが痛くなるといってました。
OAKLEYのテンプル頭の大きい人は要注意
スポーツ用サングラスは、鼻あて(鼻に当たる部分)がないタイプがあります。それはそれで普段は何の問題もないんですが、汗をかく時期はレンズが曇りやすいんです。鼻あてが無い分、顔に密着してしまって、空気が抜けないために湿気がこもるんだと思います。夏に特に汗をかくシーンで使う場合は要注意です。
OAKLEYの鼻あてこれが低いと湿気でレンズが曇る
それから、Dragonのサングラスは使っていて、UVを遮断しているという感じがしますね。なぜかというと、目の周囲全体をカバーして目の周りが日焼けしていないから。
ぼくは使ったことがないですけど、知り合いのサーファーでSmithのサングラスを使っている人がいます。
Gillはセイリング・ヨットの道具のブランドです。海で使いやすいようないろいろな工夫がされています。
ゴムのストラップがついていたり、水に浮きます。
とても軽いしかけやすいし、錆びるパーツを使っていないというのも海遊びをする人にとってはうれしいですね。
セイラーでは使っている人が多いブランドです。
最近はレンズに撥水加工がしてあるサングラスとか水に浮くサングラスというのもあります。
例えばOAKLEYのサングラスはレンズが水も油もはじく(ハイドロフォビックレンズコーティング)ものがあります。ぼくは使ったことがありませんが、一度使ってみたい気がします。
いろいろ使ってみて、使いやすかったのは、UVをできる限りカットするもの(より幅の広い波長とカット率だいたい98%以上)で、ブラウンの中ぐらいの色の濃さのレンズで、光の透過率が30~40%で、錆びやすい素材があまり使っていないもの、でした。
あと有名どころでは
720 armour(アーマー)
Eagle Eyes
RUDY PROJECT
KAENON(ケーノン)
などがあります。
でも、サングラスって、落としちゃったり、ぶつけて割っちゃったりするんで、消耗品と考えると、あまり高くないのがいいと思います。
例えばユニクロでは偏光グラスのサングラスを1000円くらいで売ってて、勢いで買っちゃいましたが、そんなに悪くないですよ。
他にもサングラスに関する記事を書いていますので、よろしければご覧ください。
・紫外線から身を守れ!
・メガネをかけている人のためのサングラス
海辺の暮らしランキングに参加しています。クリックして投票してください!
カヤックを車のルーフに積み込みやすくするキャリアパーツ
(写真はThuleのHPから転載させていただきました)
ぼくはシーカヤックをやります。地元の海でも漕ぎますし、車のルーフに乗せて他の海で漕ぐこともあります。
シーカヤックを車のルーフに積むために、ルーフキャリアをセットしてシーカヤックを積むんですが、今の車がSUVでルーフまでの高さが割とあるので、シーカヤックを乗せるときにちょっと苦労します。シーカヤック自体は重さが20kgくらいなので、苦労というほどではないんですが「よっこいしょ」くらいの頑張りが必要なんです。
で、Thuleというキャリアメーカーから、Thule Hullavator Proというシーカヤックを持ち上げるのをサポートしてくれる機能が付いている製品が販売されているんですね。ただこれが仕掛けがゴツい製品でして、価格も定価で16万5千円もするんです。
う~ん…という感じです。そんなお金を使うなら、今までのように自力でよっこいしょと乗せればいいやと思って買っていません。
ただ、たまにこのキャリアを使っている車を見かけると「やっぱりいいなー」と思ったりします。
カテゴリー
最新記事
(08/31)
(08/30)
(08/24)
(08/23)
(08/17)
(08/16)
(08/10)
(08/09)
(08/03)
(08/02)
(07/27)
(07/26)
(07/20)
(07/19)
(07/13)
(07/12)
(07/06)
(07/05)
(06/29)
(06/28)
(06/22)
(06/21)
(06/15)
(06/08)
(06/07)
最古記事
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/01)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/02)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
(07/03)
アーカイブ
ブログ内検索
PR
カレンダー
最新コメント
[10/31 TOM]
[06/10 TOM]
[06/10 TOM]
[11/09 porn]
[07/09 和]
PR
google


